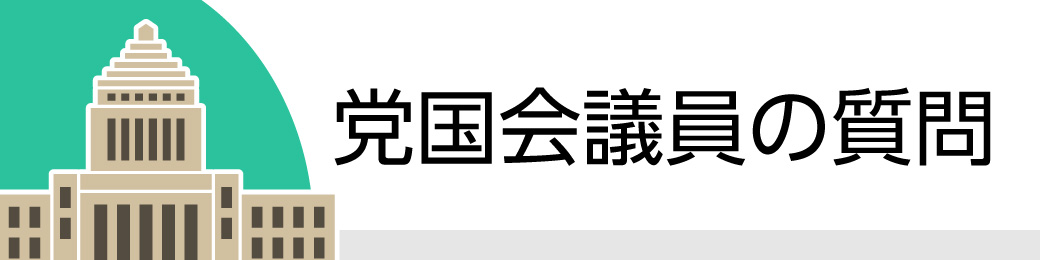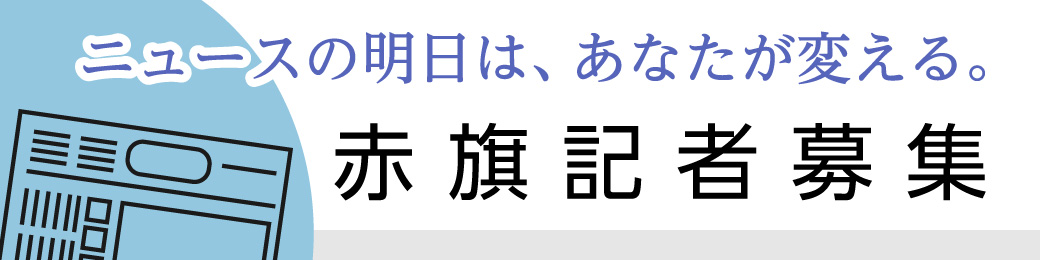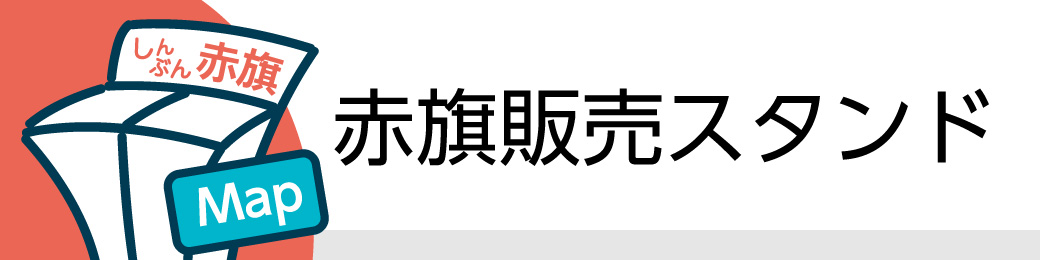2025年10月12日(日)
主張
2人のノーベル賞
基礎研究支援の強化の転機に
今年のノーベル賞が発表され自然科学分野で、生理学・医学賞は坂口志文・大阪大学特任教授、化学賞は北川進・京都大学特別教授の受賞が決まりました。革新的な研究成果で人類に貢献した偉業に心から敬意を表します。
坂口氏は、免疫の働きを抑える「制御性T細胞」を発見した功績が評価されました。大学院生のときに、免疫細胞をつくる胸腺をマウスから摘出すると、免疫が弱まるのでなく、逆に免疫細胞が自己を異物とみなして攻撃する「自己免疫疾患」となる現象に知的好奇心を持ちました。
■常識を覆す研究
この裏側にある仕組みとして、免疫反応を抑える未知の細胞が胸腺に存在し、それを取り除くと自己免疫疾患になるという仮説を立てました。「免疫細胞が正常な自己を攻撃するはずはない」という当時の常識を覆すものでした。
日本では「非常識」な研究を続けるのは困難だと考え、渡米して、8年間の奨学金を得てマウスでの実験を繰り返しました。多種類ある免疫細胞の中から免疫の働きを抑える細胞を特定し「制御性T細胞」と名付けました。学説の確立に20年を要しました。
免疫を制御するすべを得たことで、自己免疫疾患の治療、免疫細胞にがん細胞を攻撃させる治療法、臓器移植後の拒絶反応を抑えるために免疫の働きを制御する方法の開発などに道を開きました。
北川氏は、狙った物質を内部に閉じ込められる「金属有機構造体(MOF)」開発の功績が評価されました。MOFは有機物と金属を骨格とするジャングルジムのような構造です。ナノメートルサイズの均一な穴が規則正しく開いており、穴のサイズは自在に変えられます。狙った物質だけを穴に吸着させ、分離や貯蔵が可能になりました。
水からのPFASの分離、空気中の二酸化炭素の捕捉、砂漠の空気からの水の採取などが期待されます。北川氏も、論文発表直後は「常識に反する材料」と信じてもらえず注目されませんでした。
■息の長い研究こそ
2人の受賞が教えるのは、知的好奇心にもとづく常識にとらわれない息の長い研究があってこそ、人類に多大な進歩をもたらす革新的な成果が生まれるということです。
両氏とも記者会見で文部科学相に対して基礎研究への支援の強化を訴えました。
基礎研究を支える国立大学交付金などの基盤的経費を削減し、競争的資金にシフトする「選択と集中」により、任期付き研究者が増え、短期的な成果主義がまん延し、多様性が失われつつあります。
研究者1人当たりの研究費が数万円という地方国立大学すらあります。質の高い論文数の世界ランキングはこの20年で4位から13位に転落しています。これを回復するには、正規教員、研究支援者、研究時間を増やし、ゆとりある研究環境をあらゆる分野でつくりだすしかありません。
文科省は、来年度の概算要求で国立大学交付金を前年比632億円増の過去最高額を要求しました。今度こそ基盤的経費の抜本的増額に転換し、基礎研究をはぐくむ環境を回復すべきです。