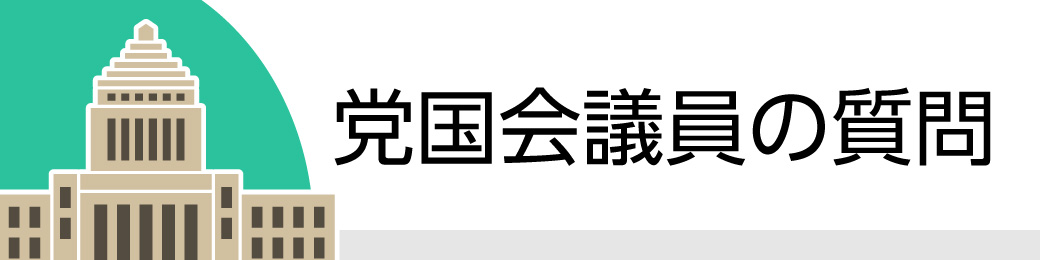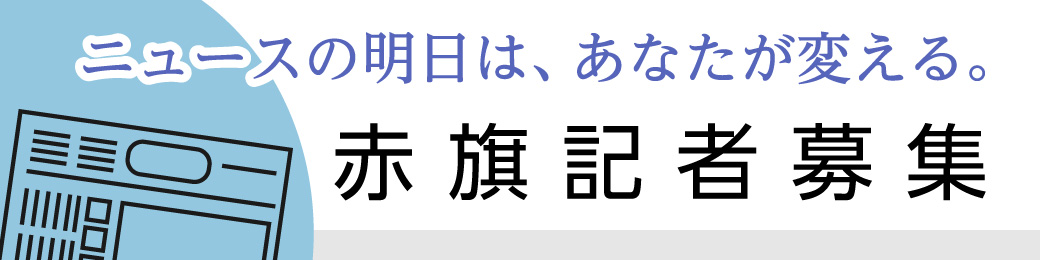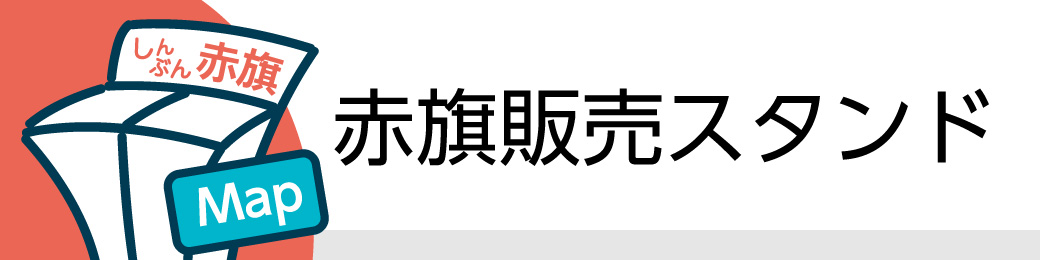2025年10月9日(木)
きょうの潮流
自然科学の研究者の世界は、寛容な社会らしい。互いの研究成果を信頼し、それを基に新たな研究の進展を図る。同時に異端の研究や最先端を開こうとして生じた間違いに対しても▼自著でもふれている、その寛容さを信じて長い冬の時代を乗り越えてきたのか。今年のノーベル生理学・医学賞に米国の研究者とともに選ばれた坂口志文(しもん)さんです。40年余にわたって過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」の研究にとりくんできました▼私たちの健康を維持するうえで大きな鍵を握る免疫システム。その暴走を抑え、免疫系の「守護者」と呼ばれている細胞です。働きを解明することで今後はアレルギーやがんの治療などへの応用が期待されています▼京大医学部を卒業後、「病の理(ことわり)」を知りたいと病理学の基礎研究の道へ。しかし追い求めた細胞の研究は注目されず、活路を求め米国へ。財団の奨学金に応募して研究を続けました▼「日本の基礎科学への支援は不足しているように感じる。ぜひとも支援をお願いしたい」。文科相との電話会談で要望した坂口さん。日本では9割近い研究者が科学研究力の低下を感じているとのアンケート調査もあり、予算も時間もない深刻なありさまです▼日本のノーベル賞受賞者が口々に訴える国の支援の貧しさ。免疫分野の研究資金はドイツの3分の1ほどだと。坂口さんの快挙に目を輝かせる若い研究者や学生ら。意欲の芽をつぶさず、自由な発想や挑戦ができる環境づくりと寛容さが求められています。