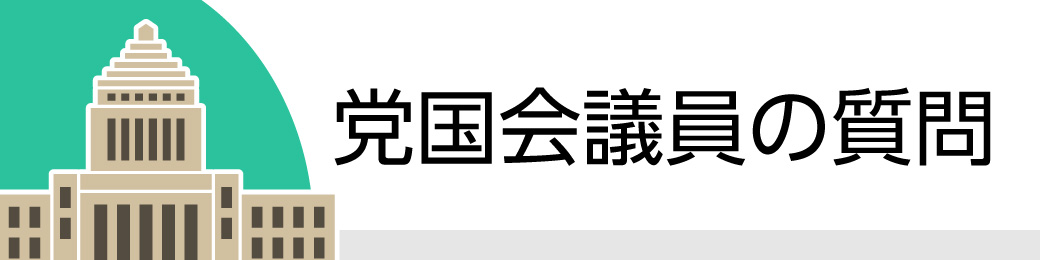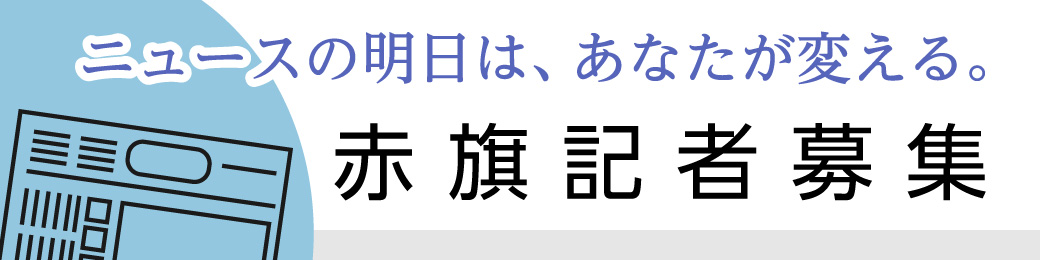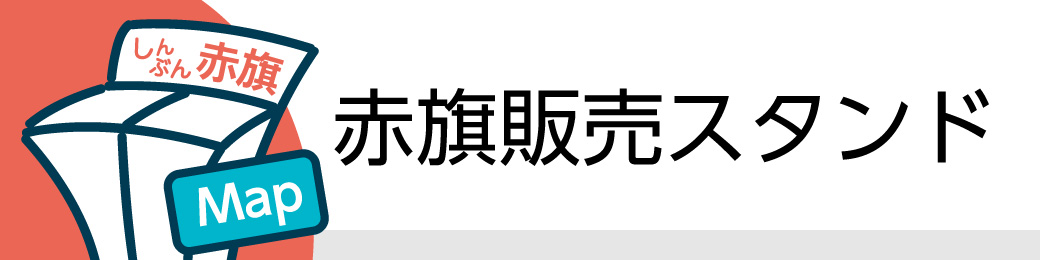2025年10月8日(水)
きょうの潮流
明烏(あけがらす)、木乃伊(みいら)取り、五人廻(まわ)し…。江戸落語の名作が高座から消えた時代があります。時は太平洋戦争の前夜、国の締めつけを前に落語界は自粛し、53種もの演目を禁演落語と定めました▼東京・台東区の本法寺(ほんぽうじ)に立つ「はなし塚」。1941年に刻まれた碑文には「葬られたる名作を弔ひ尚(なお)古今小咄(ばなし)等過去文藝を供養する為(ため)」とあり、禁じられた落語の台本が納められています。関係者の無念とともに▼前進座が公演中の「笑いごとではありませぬ!」は、笑いで戦争に協力させられた噺家(はなし)たちの葛藤や悲哀を描いています。くるわ噺や色恋ものを扱った落語を禁じる一方で、戦意高揚の国策落語がもてはやされていく姿を▼戦後80年特別企画。脚本を書いた朱海青(しゅ・かいせい)さんは戦前に創立した前進座の歴史にふれながら、「先輩たちは苦い思いをのみこみ、演じ続けた。その『笑いごとではない』過去は今を生きる私たち自身の過去なのです」▼ゲストで口演した林家三平さんは両親のすさまじい戦争体験を紹介し、代をさかのぼれば戦争の恐ろしさをみんな味わっているはず。それを伝え継ぎ、自由に話すことができなくなる時代が再び来ないように監視しなければならないと▼劇中、時勢を案じる師匠が語ります。「駄目な奴(やつ)もよし、自分もよし、あいつもこいつも足りねえところはあるけど、まあ一緒に生きていこうぜって、それが落語だ」。そして、神様だの、お上だのをむやみに奉って有り難がってる輩(やから)は、しまいにきっと間抜けな目を見ると。