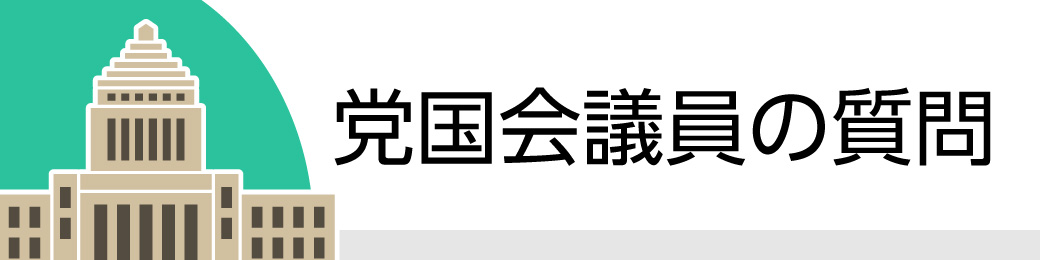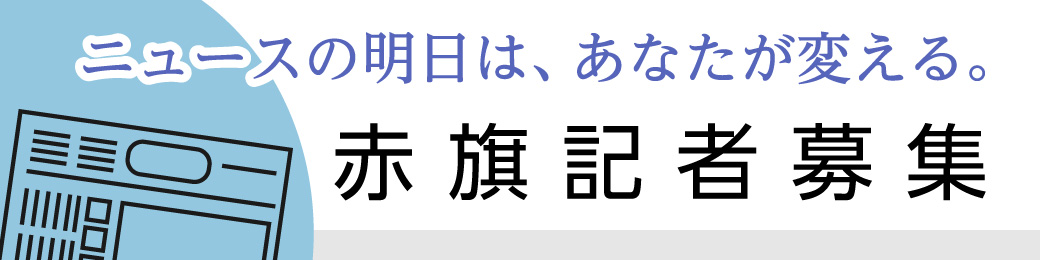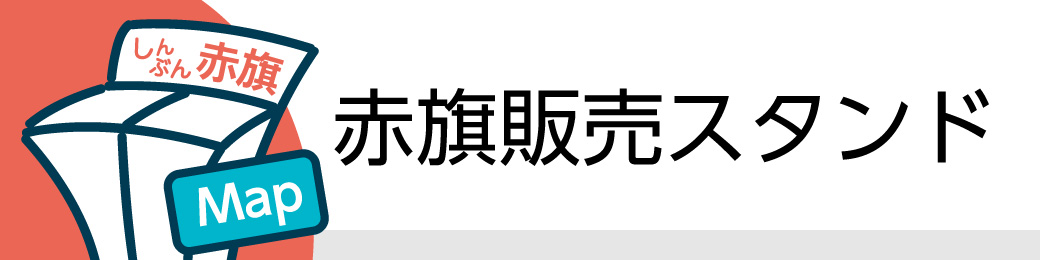2025年4月24日(木)
2025焦点・論点
学術会議解体法案 歴史の教訓は
明治大学教授(日本近現代史) 山田朗さん
学問の統制は突破口 自由奪い戦争に動員
今国会で18日、審議入りした日本学術会議を解体する法案。戦前、学問の自由を弾圧し、学問研究を戦争に動員した歴史から何を教訓とすべきか、明治大学教授の山田朗さん(日本近現代史)に聞きました。(伊藤紀夫)
 (写真)やまだ・あきら 1956年大阪府生まれ。明治大学文学部教授、平和教育登戸研究所資料館館長、博士(史学)。著書は『大元帥 昭和天皇』『軍備拡張の近代史―日本軍の膨張と崩壊』『世界史の中の日露戦争』『兵士たちの戦場―体験と記憶の歴史化』『帝銀事件と日本の秘密戦』『増補 昭和天皇の戦争』など多数 |
―2020年に政府が学術会議会員候補6人の任命を拒否した問題にフタをしたまま、独立性をもった学術会議を解体する法案で、戦前、学問の自由が弾圧された歴史が想起されます。
そうですね。学問に対する締め付けというのは、自分たちとは関係ない世界だというふうに見えがちです。しかし、今までの歴史的経験から見ると、学問の弾圧・統制は突破口で、それを許してしまうと次から次へといろいろな自由がどんどん制約されていくことになります。
戦前、1933年の滝川事件は学問に対する言論弾圧の始まりでした。京都帝国大学の滝川幸辰(ゆきとき)教授は刑法学者で、政府はその学問内容が無政府主義的で共産主義に好意的だと決めつけ、その著作を発禁処分にし、大学から追放しました。法学部は教授会も学生も一丸となって反対しましたが、結局敗れてしまいます。
35年の天皇機関説事件は当時、憲法学上有力とされた「天皇機関説」、つまり天皇は国家の一機関であるとする学説が天皇絶対の「国体」に反するとして弾圧された事件です。その学説の代表者である美濃部達吉貴族院議員・東京帝国大学名誉教授は「学匪(がくひ)」と攻撃され、政府はその著作を発禁処分にし、公職から追放しました。
―そのうえ政府は35年に2度も「国体明徴(めいちょう)に関する政府声明」を出して、全国の教員に対して天皇機関説の教授を禁止しましたね。
そうなると、それが基準になり、あの学問は「国体」に反している、この宗教は「国体」に反していると弾圧対象が拡大していく。実際、天皇機関説事件とほぼ時を同じくして大本教が弾圧されました。宗教弾圧は人の内面に対する統制で、あらゆる宗教活動が制約を受け、自分たちの宗教が「国体」に反していないという証しを立ててアピールしないといけなくなります。結局、社会全般の自由が圧殺されていきます。
25年に制定された治安維持法による日本共産党などへの弾圧とともに、個人の思想・価値観に踏み込んだ統制によって何か言うと「非国民」と言われるような国民が相互に監視し合うシステムが出来上がっていったのが30年代半ばでした。
―今回の法案の背景には、「安全保障技術研究推進制度」(2015年発足)で防衛省が資金を出して研究に介入する問題など、学問を軍事利用する狙いがあります。山田さんは明治大学平和教育登戸研究所資料館の館長ですが、戦前、陸軍登戸研究所が学者や技術者を動員して電波兵器や毒物・細菌兵器など秘密戦兵器を開発していた歴史について教えてください。
 (写真)風船爆弾の10分の1模型を見学する人たち(明治大学平和教育登戸研究所資料館提供) |
まさに陸軍登戸研究所は軍産学共同の典型事例です。そこで働いていた中堅幹部層を見ても、もともとの軍人は少なく、現場の責任者は民間人で、研究機関や大学、一般企業に勤めていた人たちがヘッドハンティングされて軍人の肩書を与えられた人たちでした。
完全に国家に統制された学問のもとで暗殺用毒物の開発を進め、早く結果をだすために中国で捕虜や死刑囚を使った人体実験を平気でやったのです。戦争に科学が動員されると、国家のためなら手段を選ばず、何の歯止めもなくなります。
風船爆弾も最初は、細菌兵器を積み、米国中にペスト菌をばらまく計画でした。技術的に不可能だとわかったら、牛疫ウイルスをまいて米国の食料に大打撃を与える研究を44年まで続けます。一応めどが立ちますが、敗戦の色が濃くなる中で米国の報復を恐れ、焼夷(しょうい)弾を積んだ無差別攻撃に切りかえました。戦争に勝つかどうかが最大の基準で、人道や倫理などはおかまいなしだったのです。
戦後、米国は人体実験を行った731部隊(関東軍防疫給水部)も登戸研究所も情報提供と米軍への協力と引き換えに免責しました。そこで働いた研究者たちは戦犯にされませんでしたが、自分たちがやったことを何も語れず、ずっと心の中に闇を抱え重荷を背負って生きてきたわけです。
だから、登戸研究所資料館が2010年にできて登戸研究所に勤めていた人たちが見学に来た時、「こんな資料館ができたってことはもう話していいんだね」「ほっとした」と一様に語っていました。
登戸研究所に勤め陸軍技術少佐だった伴繁雄さんは89年に高校生たちの度重なる熱心な要請を受けて登戸研究所のことを語り始めますが、人体実験の話はできなかった。その後、『陸軍登戸研究所の真実』という著作の中で人体実験について証言し、「戦争の暗黒面としてこれまで闇の中に葬り去られてきたが、いまこのいまわしい事実を明らかにしたい」「平和を心から願う気持ちである」と書いています。
―学問が弾圧され、科学の軍事利用が進むとどうなるか、歴史の事実は雄弁に物語っていますね。その教訓から、今回の法案をどう見ていますか。
学術会議は政府の従属物になってはならず、独自性を保ってこそ社会的な役割を発揮できるということです。政府が学術会議を支配下に置く今回の法案が通れば、政府の意向にそった限られた意見しか出てこず、その結果、国が大きな過ちを犯し、国民に損失を与えることになると思います。
政府が「国民を統制しますよ」と言ったら、みんな反対するから、「いや、これは特殊な学問の世界の話だから」というふうに見せながら、法案を通そうとしているような気がします。しかし、学問は社会を土台に成り立っているものですから、学問が自由を失えば社会の自由も奪われることになります。
今、政府が大軍拡、戦争への道を進んでいる時、「軍事目的のための科学研究を行なわない声明」(67年)を出してきた学術会議を国に従属する機関にしてはなりません。
軍事研究などすぐに成果が出るものにお金を投じるやり方ではなく、基礎研究にきちんとお金を注いで学問の土台を本当に維持していくうえでも、学術会議を解体する法案を止めなければならないと思っています。