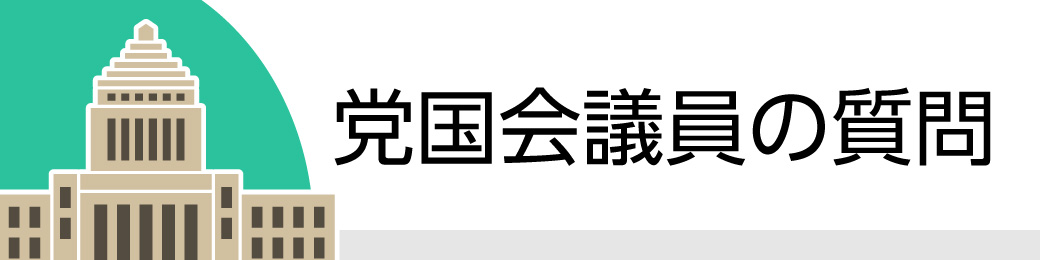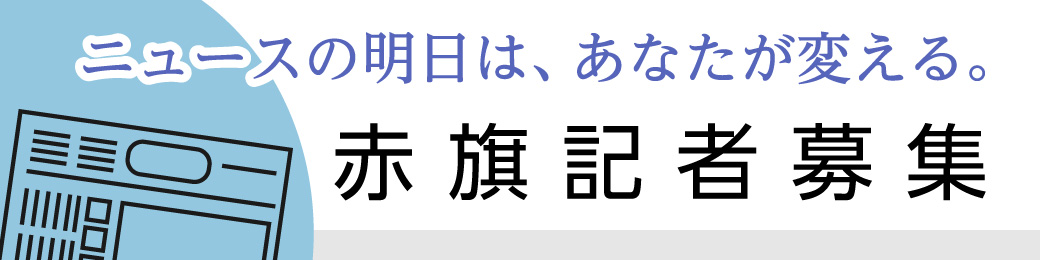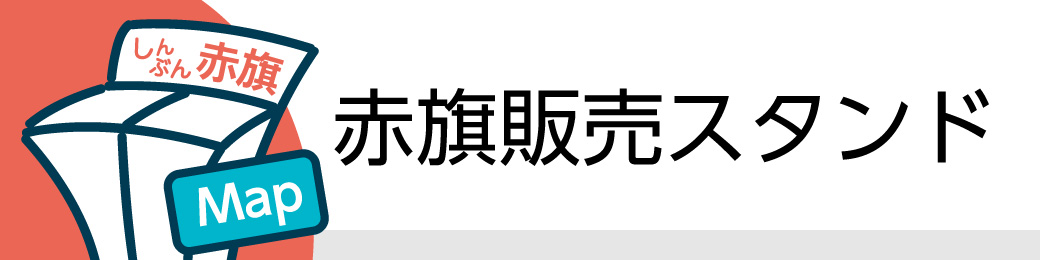2025年4月22日(火)
主張
再審制度の改正
冤罪救済へ今国会で成立図れ
再審制度の改正を求める超党派の国会議員連盟は、今国会での成立を目指し刑事訴訟法改正案の要綱をまとめました。一方、鈴木馨祐(けいすけ)法相は法制審議会に再審制度の見直しを諮問し21日、初の部会が開かれました。今国会で改正できるか焦点となっています。
有罪が確定した裁判をやり直す再審は冤罪(えんざい)救済の「最後の砦(とりで)」です。しかし、再審開始のハードルは非常に高く、「開かずの扉」とも言われてきました。制度見直しが長年求められてきましたが、これまで法務省は消極的でした。
昨年10月、死刑囚だった袴田巌さんの無罪が再審で確定したことで世論が高まり、「福井女子中学生殺人事件」で冤罪を訴えてきた前川彰司さんの再審開始の確定でさらに声が広がっています。
■証拠の全面開示を
袴田さんの場合、最初の再審請求から裁判所が再審開始を決定するまで33年かかりました。しかも検察が不服を申し立てたため、再審開始が確定し再審公判が始まるまでさらに9年半、そこから無罪確定まで1年を要しました。事件当時30歳だった袴田さんは88歳になり、長期の拘束で精神に変調をきたしました。
前川さんは一度は再審開始が決定しましたが、検察の不服申し立てを受けた審理で取り消され、2度目の請求で再審開始が確定するまで最初の請求から20年要しました。7月に再審での判決が出ます。
冤罪は国家による重大な人権侵害です。冤罪を晴らすのに人生をほぼ費やす現状は早急に改める必要があります。
長期化の主な要因の一つは、再審制度では証拠開示のルールがなく捜査当局が不利な証拠を隠したままにできることです。開示を命じるかは担当裁判官に左右されるうえ、検察は拒否できます。
袴田事件でも前川さんの事件でも、弁護団の要求や裁判所の訴訟指揮で新たに開示された証拠が再審開始や無罪の決め手になりました。再審請求手続きでの証拠の全面開示を制度化すべきです。
■検察の不服が妨げ
もう一つの大きな要因は、再審開始決定に検察官が不服を申し立て最高裁まで争えることです。再審開始を認めるかは非公開で審理され、開始が確定すると公開の裁判が行われます。検察は公開裁判で事実を争えばよく、不服申し立てはやめるべきです。
刑事訴訟法の再審に関するルールはないに等しい状況です。審理のあり方が担当裁判官次第となっている「再審格差」を改め、公正な再審手続きを整備することが必要です。
超党派議連の改正案は、▽証拠開示の規定を新設し、被告側が請求すれば裁判所は原則、検察官に開示を命じなければならない▽開始決定への検察官の不服申し立ての禁止▽審理の迅速化のため裁判所は審理期日を指定できる―などを盛り込んでいます。
法制審議会の審議は通例、何年もかかります。日本弁護士連合会は「年単位での検討を行うことは相当ではない」として議連の改正案の今国会での成立を求めています。
議連には、日本共産党の全議員のほか国会議員の半数超が参加しています。速やかに成立させることが必要です。