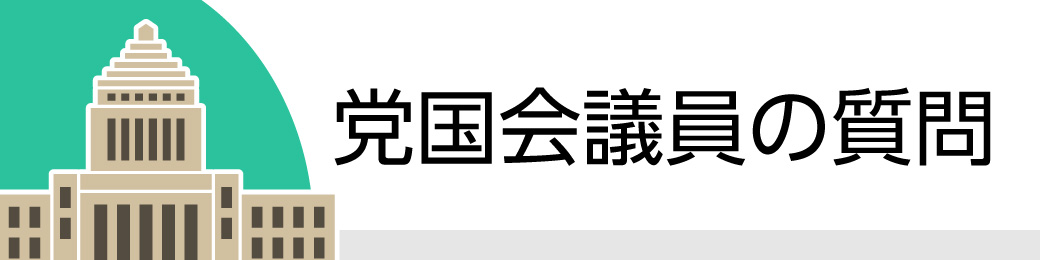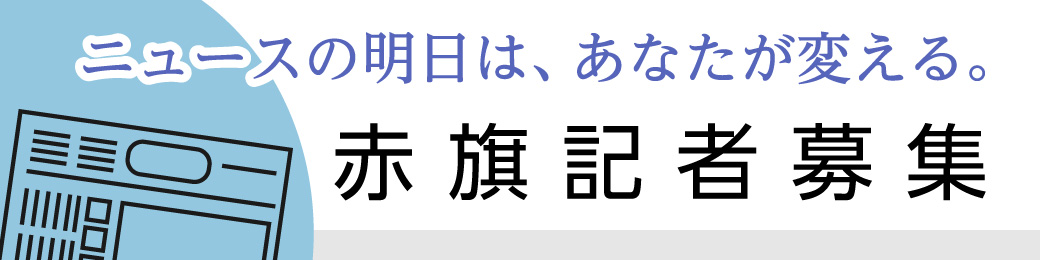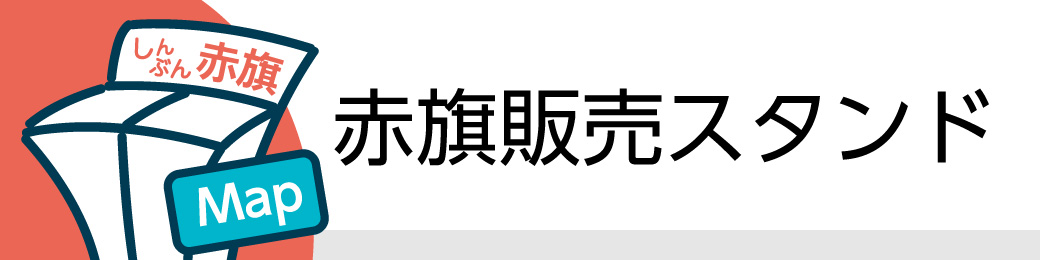2025年4月18日(金)
主張
バンドン会議70年
継承される巨大な平和の本流
植民地支配を打ち破り、独立したアジア・アフリカ諸国が結集した初めての国際会議・バンドン会議が1955年4月にインドネシアで開かれてから70年になります。同国のスカルノ大統領は「世界の歴史における新たな出発点」とのべましたが、民族の自決、平和の巨大な流れを生み出す一つの画期となりました。
■植民地体制の崩壊
当時、旧植民地の独立が相次ぐ一方、米ソのブロック対立が強まり、米国は世界中に軍事同盟網を張り巡らせ、紛争と戦火も多くありました。 こうしたもと開催されたバンドン会議には、29カ国が参加、米国との軍事同盟に加盟している国も出席しました。しかし、セイロン(現スリランカ)の首相が「平和は、力の誇示、とりわけ軍事力の誇示によっては確保できない」とのべたように、各国首脳は、勇気、他者の尊重、友好、協力など平和的手段による平和の実現を強調しました。
バンドン会議は、議論の末、意見の違いを乗り越えて最終コミュニケ「バンドン精神(宣言)」を採択しました。
そこでは、すべての民族の自決・非抑圧民族の独立と自由、すべての国家の平等と主権尊重、国連憲章に基づく国際平和秩序、自由と平和の相互依存、恐怖からの自由と平和共生・友好協力による国際平和、不干渉・大国からの自立、核兵器の禁止などがかかげられています。
「平和10原則」として、▽基本的人権と国連憲章の尊重▽国家主権、領土保全の尊重▽人種、諸国家の平等▽内政不干渉▽国際紛争の平和的手段による解決―などを打ち出しました。
バンドン会議の精神はその後、非同盟諸国会議、ASEAN(東南アジア諸国連合)などの取り組み、武力行使・威嚇の禁止など国連憲章の原則を発展させた「友好関係原則宣言」(70年)、植民地支配と奴隷制度は過去にさかのぼって非難されるべきとした「ダーバン会議」(2001年)などの国際的な取り組みに継承され、発展してきました。
■主体的・積極的に
この土台には、植民地体制の崩壊という20世紀最大の構造的な変化があります。国連加盟国193カ国のうち非同盟諸国が62%をしめるようになりました。これが核兵器禁止条約を実現する大きな力ともなりました。この発展は国連の性格を変え、多くの国が、国連憲章にもとづく平和の国際秩序を求めるなど、国際政治に積極的な役割をはたすようになりました。
いまアジアでは、一方で軍事同盟の強化、軍事対決の動きが激しくなっています。しかしASEANに見られるように軍事的対決の道でなく、包摂的な平和の枠組みを求める流れが大きく発展しています。この主体的・積極的・能動的に平和を求める動きは、バンドン精神を継承、発展させたものといえるでしょう。
いま戦争と平和の二つの潮流がせめぎ合っています。日本は、米国の言いなりに「日米同盟絶対」の立場を取り大軍拡をすすめています。しかし、そこには未来はありません。バンドン精神の流れは、歴史の本流を示し、日本がすすむべき道も照らしています。