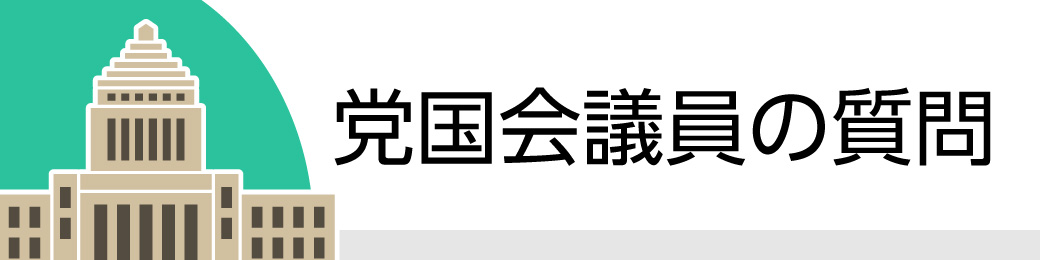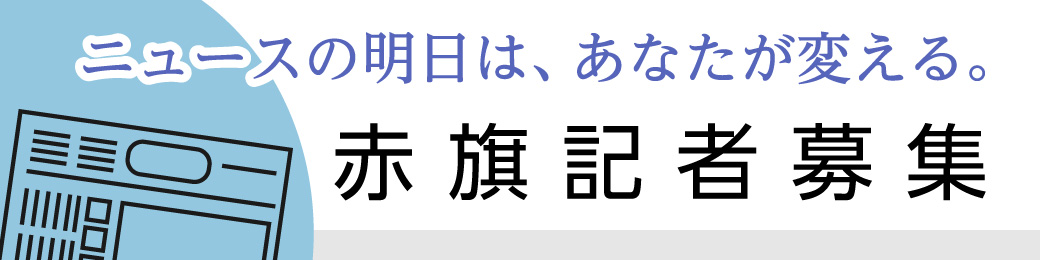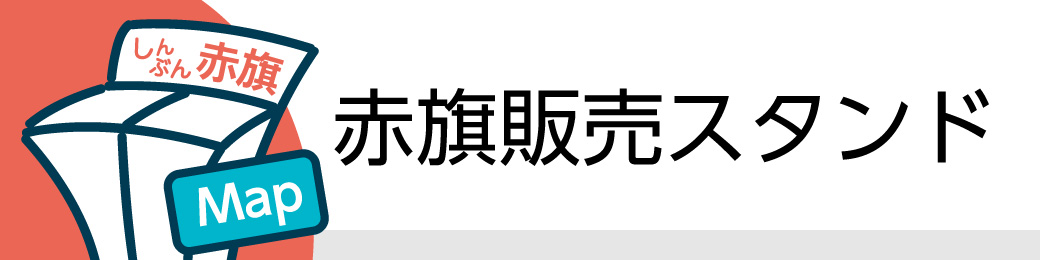2025年4月14日(月)
きょうの潮流
鉱石や真空管を使ったものや手づくりの貴重な受信機も―。戦前の草創期から現在に至るまで、ラジオの歴史がたどれる場所が長野の松本市にあります▼その名も日本ラジオ博物館。明治時代の土蔵を改良した館内には、館長の岡部匡伸(ただのぶ)さんが集めた機器や寄贈された往年のラジオが所狭しと並んでいます。いまそこでラジオ放送百周年記念展が開かれています▼1920年、米国で世界最初のラジオ放送が始まり、その5年後に日本でも放送開始。当時の聴取者はわずかでしたが、すぐに人気となり急速に普及していきます。しかし戦時下では情報の統制に使われ、国民を戦争に駆り立てる道具とされました▼戦後、情報や娯楽の中心となったラジオは人々の生活と深くかかわるようになります。のちに放送の主役をテレビに奪われましたが、ニュースや交通情報、音楽や好みの番組を楽しむファンは根強く、防災などにも役立っています▼「自分の言葉で話して、聴いている方が想像力をたくましくする」。自身の番組を45年にわたって続けた秋山ちえ子さんは、ラジオの魅力をそう語っていました。同じく長年携わった永六輔さんは「ラジオにはほっとする言葉遣いと音楽があり、語りかける人への信頼感がある」と▼4月はラジオも改編期。心ひかれるどんな番組が…。秋山さんはラジオ人として、二つの軸を大切にしていました。一つは戦争のない世界をつくりたいということ。もう一つは、取り残される人がいない社会をつくることです。