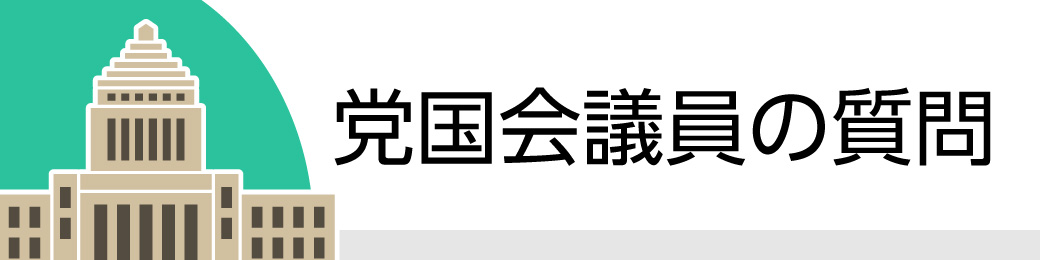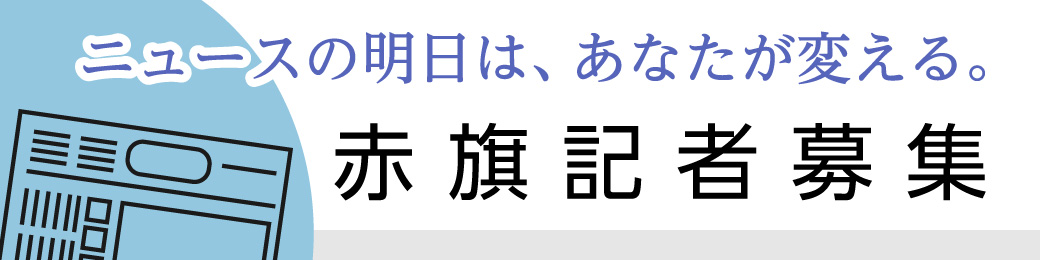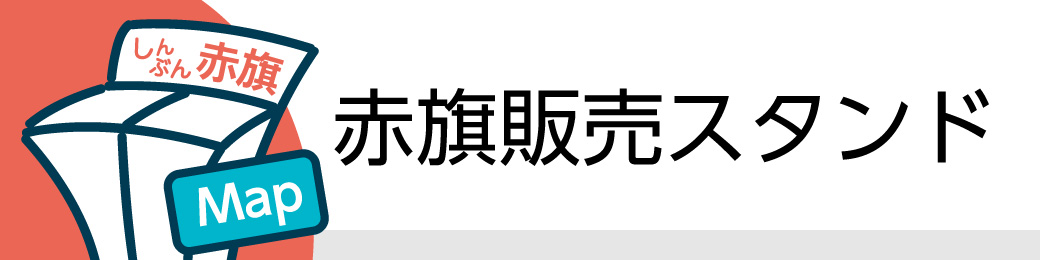2025年4月11日(金)
薬機法・医薬品承認要件の規制緩和
患者へのリスクの懸念
衆院厚労委 田村貴昭氏が批判
 (写真)質問する田村貴昭議員=9日、衆院厚労委 |
日本共産党の田村貴昭議員は9日の衆院厚生労働委員会で、医薬品医療機器等法(薬機法)改定案で薬事承認についての規制が緩和され、がん患者などに有効性が不確実な薬が投与される懸念があると批判しました。
がんなどの重篤な疾患や患者数が少ない疾患については、新薬の臨床試験を一部省略し、承認後に必要な試験を行うことができる「条件つき承認制度」があります。改定案では、承認申請の際に必要な検証的臨床試験を行う条件があっても、実施せずに承認できるよう規制を緩和し、米国の迅速承認制度と同様の仕組みにします。
田村氏は、米国では、迅速承認制度で承認された多くの抗がん剤が、市販後に有用性を示せなかったとの調査報告を示し、今回の改定で、日本でも有効性が不確実な新薬が流通し、患者に長期間投与されると指摘。国内でも既に期限・条件付きで承認された医薬品にも、市販後に有効性を示せず、何年間も公的保険財政から支出されていた事例があり、同様の可能性が広がる仕組みは問題だと強調しました。
また、通常の薬事承認についても、申請時の臨床試験成績を必須とした条文を削除し、省令に委ねる改定が含まれます。田村氏が「有効性、安全性を確認するのに、ランダム化比較試験(治療法の効果を検証する試験)を経なくても承認されるのか」とただすと、厚労省の城克文医薬局長は「あり得るか、ということであればあり得る」と答弁。田村氏は「例外の範囲をどこまでも広げる改正で、有効性、安全性をないがしろにする規制緩和は認められない」と批判しました。
また田村氏は、海外で開発された新薬が日本で承認されない、日本に入ってこないという「ドラッグ・ラグ」「ドラッグ・ロス」問題の背景には、米国では医療研究予算が7兆円に上るのに、日本ではわずか2千億円と貧弱な実態があるとして、臨床試験を実施する環境整備のための予算の抜本的拡充を求めました。