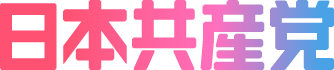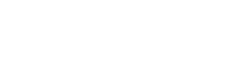89、空襲被害者等の救済のために
空襲被害者等の救済と補償を実現します
2024年10月
アジア太平洋戦争の終結から79年以上が経過しました。日本軍国主義の侵略戦争によってひきおこされた爪痕は、アジア諸国だけでなく、日本国内にもいまだに深い傷跡を残しています。その最たるものが、戦中、日本国内400市町村以上で無差別におこなわれた米軍による空襲です。原爆の犠牲者を含め、およそ50万人もの民間人の命が奪われました。正確な犠牲者数はいまだ不明です。日本政府による実態調査がおこなわれていないからです。
「戦後80年」まであと1年となった2024年8月、空襲などの戦争被害者4団体は、残された戦後処理問題の解決を求める要請書を提出しました。
救済の責任は日本政府が全面的に負うべき
日本各地への空襲は、無防備都市に対する無差別攻撃であり、当時も国際法違反でした。その意味では、空襲被災者はハーグ陸戦条約3条により国際法違反の空襲を行った米国政府に請求する権利がありました。しかし、日本政府はサンフランシスコ講和条約によって、米国への賠償請求を放棄し、空襲被害についても、国際法上の外交保護権を放棄しました。
また、日本政府は戦時中の1937年に防空法を制定し、1941年11月の改定で退去禁止と消火義務を追加しました。違反者の処罰も規定し、空襲時には「逃げるな、火を消せ」と命じました。大阪地裁と同高裁は、国策によって国民が危険な状態に置かれた事実を認めています。
日本政府が空襲被害者の救済に全面的に責任を負うべきことは当然です。 ところが、「戦争の犠牲や損害は、非常事態のもとでのことであり、国民がひとしく受忍しなければならなかった」(戦争被害受忍論)などと空襲被害者への補償を拒否し続けてきました。その一方で、旧日本軍人・軍属にたいしては、これまで総額約60兆円にも及ぶ補償金が支払われてくるなど、ダブルスタンダード(二重基準)の姿勢をとり続けてきました。
政治決断で直ちに実現を
超党派「空襲議連」は2021年3月の総会で、「特定戦災障害者等に対する特別給付金の支給等に関する法律案(要綱)」を承認。① 特別給付金を「特定戦災障害者等」(PTSD=心的外傷後ストレス障害を含む)に支給する、② 政府は空襲等による被害に関する実態調査および追悼施設の設置を行う―ことを求めています。これらの課題は、政治が決断すればすぐにでも実現できるものです。「空襲議連」は2022年にも空襲被害者救済法の早期成立を訴えています。
日本共産党の笠井亮衆院議員(「空襲議連」副会長)、「救済法の成立は国として二度と戦争の惨禍を繰り返さないという政治の決意の証し」とのべ、戦争の惨禍をひきおこさないという憲法前文の精神のもと、空襲被害者等の救済と補償実現のために奮闘する決意を語っています。