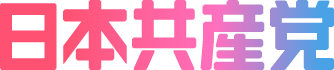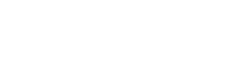日本共産党創立103周年記念講演
日本共産党はどういう党か――歴史的岐路での役割
幹部会委員長 田村智子
2025年9月23日
みなさん、こんにちは(「こんにちは」の声)。田村智子です。記念講演会へのご参加、ありがとうございます。そして、日本共産党へのあたたかく、力強い応援メッセージをいただいた4人のみなさまにも、感謝を申し上げます。ありがとうございました。
まず、7月の参議院選挙でのご支持・ご支援に、心から感謝申し上げます。自民党・公明党を参議院でも少数に追い込むうえで、私たちは、大きな役割を果たしたと確信していますが、日本共産党の議席を減らす、大変厳しい結果となりました。
9月初め、第6回中央委員会総会を開催し、参議院選挙の総括とともに、いま日本共産党がどういう役割を果たすべきか、そのために何をするのかなど、2日間かけて、とことん議論を行い、反省点と前向きの教訓を導き出し、今後の活動の方針を決定しました。
「いま、日本共産党が、がんばらずしてどうするか!」「強く大きな党をつくって、必ず選挙で勝利しよう」--この決意があふれる6中総決定を、きょう、ご参加のみなさんにもぜひお読みいただきたいと思います。そして、私も、熱い決意を決して冷ますことなく、決定の実践に全力をつくすことを、まず表明するものです。
きょうの記念講演のテーマは、「日本共産党はどういう党か--歴史的岐路での役割」としました。
歴史的岐路とはどういうことか。一方で、自民・公明が少数に転落した、他方で、自民党の補完勢力=アシストしてきた政党、また極右・排外主義の立場に立つ政党が議席を伸ばした--自民党政治を終わらせて新しい政治へと向かうのか、それとも、自民党が補完勢力や排外勢力とブロックをつくって自民党政治をより悪い方向へと向かわせてしまうのか、日本の政治が重大な分かれ道にあるということです。
この歴史的岐路のもとで、日本の政治をどちらの方向に進めようとするのか、いま、すべての政党が真価を問われている、この観点から、日本共産党そのものについてお話ししたいと思います。
1 政治の行き詰まりと危機を、国民との共同によって打開する党
第1に、日本共産党は、政治の行き詰まりと危機を、国民との共同によって打開する党です。私たちの綱領には、統一戦線--思想信条の違いを超えて、一致する目標や要求で共闘し、政治を変えていくという立場が明記されています。さしあたっての緊急の課題でも、本格的な政治の改革でも、さらには将来の社会主義変革を進めるさいにも、つねに要求にもとづく国民との共同、統一戦線によって政治を前へ動かすために力をつくす、それが日本共産党です。
安保法制が強行された2015年9月19日には、「戦争法(安保法制)廃止の国民連合政府」をよびかけました。国会を包囲した「安保法制反対」「憲法守れ」「野党は共闘」、この声--いまでも思い出すと胸が熱くなりますが、この声に応えた私たちの新しい挑戦でした。それから10年、市民と野党の共闘は、これを恐れる勢力から激しい攻撃を受け、さまざまな困難や曲折を経験しましたが、全国に広がり、あきらめることなく共闘への努力がなされたからこそ、今日、衆議院でも参議院でも、自民党・公明党を過半数割れに追い込むことができたのではないでしょうか。(拍手)
いま、自民党政治はいよいよ行き詰まっています。昨日(9月22日)から、自民党総裁選挙が始まりましたが、何か期待できるところがあるでしょうか。裏金に無反省、物価高への対策はない、トランプ大統領いいなりで大軍拡を進める、そして、排外主義と対抗する姿勢を持たないどころか迎合していく--どの候補者も同じです。「政治を変えてほしい」という国民の要求に応えるすべをもっていません。いまの深刻で危機的な行き詰まりを打開するには、自民党政治そのものを終わらせる以外に道はないことが、いよいよ鮮明となっています。
私は、昨年1月の第29回党大会で、「日本の政治のかじ取りを自民党に任せていいのかが根底から問われている」「自民党政治を終わらせる国民的大運動を起こそう」とよびかけました。ここで、手をゆるめるわけにはいきません。衆参両院で自公を少数に追い込んだいまこそ、切実な要求の実現を迫り、自民党政治を終わらせるために、共同の力で政治を前へ動かそうではありませんか。(拍手)
“反動ブロック”の危険に立ち向かう“新しい国民的・民主的共同”を
いま私たちは、今日の情勢のもとで新しい共同をよびかけています。
参議院選挙で議席を伸ばした国民民主党や参政党などには、自民党政治を終わらせるという立場はありません。自民党は、総裁選の各候補者が、維新の会や国民民主党、参政党に公然と秋波を送っています。維新・国民民主からは、呼応する言動がさまざまに出てきています。また、参政党は、アメリカやドイツの極右勢力と連携する動きをみせています。
こうしたことから、第6回中央委員会総会では、「自民党・公明党と、維新の会、国民民主党、参政党などによる“反動ブロック”が形成され、社会保障など国民生活の破壊、大軍拡の暴走、憲法と民主主義の蹂躙(じゅうりん)、ジェンダー平等への逆流など、日本の政治に深刻な逆行をもたらす危険が生まれている」と警鐘乱打し、「“反動ブロック”の危険に正面から対決する“新しい国民的・民主的共同”をつくろう」とよびかけたのです。
“反動ブロック”の危険は、決して軽視することはできません。これらの政党は、参議院選挙でも、医療費大幅削減を競うように主張しました。医療の基盤を崩壊させる社会保障大改悪のきわめて危険な動きです。大軍拡、憲法改悪に突き進む立場も同じです。そしてスパイ防止法制定を、これも競い合って主張し始めました。国民を監視し、知る権利や報道の自由を奪うスパイ防止法は、1980年代に制定が狙われ、国民的な運動でこれを打ち破ったことを、私もよく覚えています。当時、統一協会が、スパイ防止法の火付け役であったことも指摘しなければなりません。
暗黒の時代への逆行の危険が進んでいるとき、立場の違い、党派の違いを超えた国民的な共同で立ち向かおう--私たちのこのよびかけに、わずか2週間で連帯、歓迎、また共鳴する声が次々と寄せられています。
総がかり行動実行委員会の高田健さん--「安保法制=戦争法を廃止し、憲法が生き、命と暮らしを守る政治に変えるため、平和を願う若い世代などと、新しい共同を広げていきたい」。法政大学元総長で名誉教授の田中優子さん--「今こそ国民が力を合わせて声を上げ、非暴力による協力と共同によって、戦争への道を押し止(とど)める時」だ。いずれも「しんぶん赤旗」に寄せていただいた声です。「戦争法廃止!9・19国会正門前大行動」でも、新しい連帯・共同をよびかけるスピーチが相次ぎました。上智大学教授の中野晃一さんは、「みなさんの中には、『同じことばかりやっていても、うまくいかない』と自信をなくしている人もいると思いますが、それが世界を好転させていくとしたら、これしか希望はない。私たちが下からもう一回、連携をつくり直し、大きな共同をつくっていかなければいけません」、そう指摘されました。
野党のなかにも共感が広がっています。先週18日、立憲民主党の野田佳彦代表ら新役員との懇談で、私は、「衆議院に続いて参議院でも自民党を少数に追い込んだ。自民党政治を終わらせるために力を合わせましょう」、また、「極右的な流れに対抗するために力を合わせましょう」とよびかけました。野田氏は、「打倒、自民党」「打倒、右派・ポピュリズムでやっていきたい」と応え、共同への重要な合意を確認しました。
私たちのよびかけを受け止め、応えるたくさんの市民のみなさんがいる、政党がある。日本共産党が、国民との共同で政治を変えるという綱領を土台に、この10年間、市民と野党の共闘への努力を貫いたことで、新たな共同へと発展する可能性が、いま目の前に広がっていると思います。「ここにこそ、危機も行き詰まりも打開する展望がある」--このことを確信に、必ず新しい共同を大きく広げる決意です。ご一緒にがんばりましょう。(大きな拍手)
2 自民党政治のゆがみを根本からただし、新しい政治への希望を拓く党
第2に、いま、自民党に厳しい審判が下り、自民党政治に代わる新しい政治はどういうものかが問われていますが、「財界・大企業最優先」「異常なアメリカいいなり」という、自民党政治の「二つのゆがみ」を根本からただし、新しい政治へと改革する綱領を持っているのは、日本共産党をおいて他にはありません。
私たちが、長年にわたって告発してきた「二つのゆがみ」は、いま、誰の目にも明らかとなり、日本共産党とはかなり立場の違う人たちからも、これで良いのかという指摘がされるまでになっています。私たちの綱領路線が、力を発揮する時を迎えています。
「失われた30年」は、「財界・大企業最優先」の経済失政
「財界・大企業最優先」の政治は、経済失政、経済無策となって、「失われた30年」をもたらしました。日本共産党はこれまでも、多岐にわたる問題を告発してきましたが、きょうは、(1)所得の再分配の機能が壊されている、(2)ひどい搾取によって所得そのものが奪われている--この二つの視点でお話をしたいと思います。
所得再分配の破壊――消費税増税と社会保障の連続削減
税制と財政が果たすべき役割の一つは、負担能力に応じた税制や社会保障によって、所得を再分配し、格差を是正し、すべての人の暮らしや生業(なりわい)を守ることです。ところが「財界・大企業最優先」の政治が、この役割を大きく壊してしまいました。
消費税の導入と引き上げは、法人税率の引き下げをはじめとする大企業減税、所得税最高税率の引き下げと富裕層への税優遇とセットで行われてきた、この30年間で、消費税の増税は3回、法人税率の引き下げは実に7回に及びます。所得の少ない人ほど負担の重い消費税を増税し、もうかっている大企業と富裕層には減税--これでは、税制による所得の再分配がズタズタに壊されるのは当然のことです。
昨年から今年にかけて、日本共産党は国会論戦で、消費税減税を迫る怒濤(どとう)の質問を繰り広げましたが、消費税の負担が重すぎて、税全体の負担割合が所得200万円以下の世帯も、800万円の世帯もほぼ同じ、いまや税負担の累進性まで失われている--この新しい資料を独自の調査で示したときには、ここまで所得再分配の機能が壊されたのかと、私自身も衝撃を受けながらの質問となりました。
また、史上最高の利益を上げているのに、大企業減税をまだ続けるのか、大企業には税金を今より負担する力=担税力があるのではないか。この点を国会質問でも、参議院選挙の党首討論でも、「逃がしてなるものか」という思いで追及し、ついに、石破首相も「大企業には法人税を負担する力がある」と認めざるを得なくなった--これはぜひ、総理が誰になろうと、次の国会につなげていきたいと思います。日本共産党の怒濤の追及のもとで、いま、他党からも、大企業への税負担を求める声が、公然とあがるという変化も生まれています。
それだけではありません。あの経団連も、昨年12月の「提言」で、「日本は以前のように格差の低い国ではなくなった」として、ついに超富裕層への課税強化を提案しました。もちろん、消費税増税も合わせて要求しているので、要注意の「提言」なのですが、少なくとも、所得再分配機能が崩されていて、格差が広がっていることを経団連も否定ができなくなったのです。
世界でも、富裕層に負担を求める声が次々と上がっています。G20首脳会議は、昨年、超富裕層への課税を目指すことを合意しました。これを受けて、スペインとブラジルは、7月1日、世界で拡大する貧富の格差の是正に向け、最富裕層への課税を促進する共同提案を発表しました。スペインの財務次官は、「効果的に富裕層に課税し、不平等とたたかい、税制をより公正で累進的なものとするためには、政治的意志が必要だ」と述べています。日本の財務次官から、このような主張が出てきたら、拍手喝采ではないでしょうか。
日本でも大きな変化を起こす可能性が生まれています。消費税は36年間の歴史の中で、初めて、減税を公約した議員が衆議院・参議院ともに多数となりました。全ての野党が、公約に責任を負っているのですから、「消費税減税を実現せよ」「公約守れ」と迫りに迫りたいと思います。同時に、公正な税制への改革へ、これまでに倍して、「消費税は廃止を目指して緊急に5%へ。税金は、大企業・富裕層の利益にふさわしい課税を」--「財界・大企業優先」のゆがみをただす改革を断固として求める決意です。
所得再分配は、社会保障制度によっても行われるべきです。自民党政治は、消費税減税を社会保障を理由に拒否しながら、消費税36年の歩みのなかで、医療・介護・年金、何か一つでもよくなったでしょうか。医療・介護、年金すべて、国民に「自助努力」「自己責任」を押し付け、負担増、給付減を続けているではありませんか。税制での所得再分配も、社会保障による再分配も、両方壊してきたのが自民党政治にほかなりません。
いま、全国知事会も、国民健康保険に国費を入れてほしいと要望し、医療・介護の危機に、ただちに対策をとってほしいと緊急要望までしています。
税金の集め方と使い方の抜本的な改革、そして社会保障の削減から拡充への転換で、壊された所得再分配を立て直そう--これが国民多数の願いに応える道ではないでしょうか。(拍手)
あまりにもひどい搾取――労働者にもっと富の分配を
「財界・大企業最優先」の政治は、所得の再分配を壊しただけでなく、労働者への富の分配を奪ってきました。
9月1日、財務省が「法人企業統計調査」結果を発表して、2024年度の労働分配率が、1973年度以来の低水準となったことがニュースになりました。労働分配率というのは、本来は労働者が生み出した付加価値を、労働者と資本家が生み出したんだという考え方に立って、役員報酬も分配のなかに含むなど問題がある指標ですが、それでも搾取の実態を暴いています。規模別でみると、中小企業の労働分配率は75・6%、大企業といえばわずか37・4%と、あまりに低い数字で驚きました。しかも、2012年度の50%台から大幅に減少しているのです。
いったい労働者が生み出した富は、どこにいったのでしょうか。同じ2012年度から24年度で、大企業の純利益は4・6倍、株の配当は2・8倍、ところが従業員の給与は1・1倍と変化がありません。労働者が生み出した富が、大企業を大もうけさせ、株の配当も大幅に増やしたのに、肝心の労働者には回ってこない--あまりにもひどい搾取です。
大企業の労働分配率をもっと長いスパンでみると、非正規雇用が増加するのに合わせて、下降傾向になっています。「財界・大企業最優先」の政治が、派遣労働法の規制緩和を進め、非正規雇用を増やして、搾取強化の旗振りをしてきたことは明らかです。
特に、就職氷河期といわれる期間(1993~2005年)に、派遣対象業務の拡大(1996年)、派遣対象業務の原則自由化(99年)、製造業派遣の解禁(2003年)と繰り返され、そのたびに非正規雇用は増えていきました。大学を卒業して最初の働き方が派遣や契約社員、その後も、非正規から抜け出すことができない方々が、この時期、大量に生み出されてしまいました。いまも、将来の希望が見えず、生きづらさを抱える方々からの怨嗟(えんさ)ともいえる切実な声が、私たちにもたくさん寄せられます。若者の人生を傷つけ、一生涯にもわたる不利益をもたらした政治の責任は、あまりに重いと言わなければなりません。
このあまりにもひどい搾取の強化は、正規雇用の労働者にも容赦なく行われています。それが、長時間労働のまん延です。1日8時間労働制の例外として、裁量労働制、「残業代ゼロ制度」がつくられ、さらに「1日8時間労働」制を崩して、労働時間を管理しない働き方までつくろうとする、こうした労働法制の規制緩和は、割り増しの残業代を払わなくてよい、業務量にふさわしい、つまり定時で帰れる人員配置をしなくてよい、という人件費コストカットの手段となり、過労死やメンタル疾患など、命と健康を犠牲にした搾取の強化となっています。また、家族との時間を奪い、自分のための時間を奪い、豊かな人生を奪う搾取となっているのではないでしょうか。
「人間らしい働き方を保障するルールをつくろう」「賃上げと一体に労働時間の短縮を」「非正規ワーカーの待遇改善を」--こうした私たちの政策は、「ひどい搾取とたたかって、富を働くものの手に」という労働者階級へのたたかいのよびかけでもあります。
最近、こうした改革の必要性をあらためて痛感する出来事がありました。フランスのインターネットメディアの記者から、日本の政治情勢を教えてほしいということで取材を受けたのです。「日本共産党がなんで怖いと言われるのかが理解できないんです。こんなに良い政策を掲げているのに」と言ってくれるまっすぐな記者さんです。日本共産党の政策の話にもなりました。働いて食べて寝るだけの生活でいいのかという私たちの問いかけが、日本の労働者に響くんですよという話をしましたら、彼女は、「信じられない」と声をあげたのです。フランスでは人生を楽しむために働く、それが当たり前だ。しばらく、そのことで話が弾んでしまいました。
日本でも、なんのために働くのか--豊かな人生のため、自分の時間を自由に使うため、そう言える社会へと改革しようではありませんか。(拍手)
国際的な孤立と“落日”――こんな米国トランプ政権に黙ってついていくのか
「アメリカいいなり」でいいのか、日本共産党のこの問いかけが、いま立場の違いを超えた共通の認識になっています。
21日付の読売新聞に、アメリカの政治哲学者フランシス・フクヤマ氏の論説が掲載されました。私たちとかなり立場の違う論者です。まずタイトルがすごいですね。「超大国の急速な自己破壊」、書き出しはこうです--「ドナルド・トランプ米大統領が1月20日に就任して8か月。世界は、まさに常識外れを目撃し続けている。いかなる外部勢力とも無関係に、新政権は自らの手で超大国の急速な凋落(ちょうらく)をもたらしている」
この論説の中でフクヤマ氏があげた事例は、トランプ大統領が、ノーベル平和賞を露骨にほしがって、インドのモディ首相に電話をしたんだそうです。そして、5月に起きたインドとパキスタンの軍事衝突を止めたのは自分の手柄だと認めろと主張した。モディ首相が「とんでもない」と拒否すると、激怒したトランプ大統領が、インドへの関税を50%に引き上げたという内容です。「国益より個人の利益追求」と酷評する論評となっています。
日本共産党は今年1月、トランプ政権が発足したときに、「今日の世界は、アメリカ一国によって動かされるような世界ではない」と表明しました。そして3月には、「アメリカ帝国主義の落日が始まった」と述べました。落日、凋落、ここにいまのトランプ大統領のアメリカの姿があります。こんなトランプ氏のアメリカにいつまでも唯々諾々(いいだくだく)と付き従う日本でいいのか。いまの日本の政治の大問題ではないでしょうか。
イスラエル支持で孤立するアメリカ――問われる日本の姿勢
緊急の課題として、イスラエルのガザへのジェノサイドの問題について述べます。
イスラエルによるパレスチナ・ガザ地区への大規模な軍事侵攻は、凄惨(せいさん)を極めています。建物という建物は破壊され、連日、犠牲者は増え続け、ガザの市民は絶望的な避難に追い立てられています。国際社会が結束して、一刻を争ってイスラエルのジェノサイドを止めなければなりません。ところがアメリカは、18日の国連安全保障理事会の緊急会合で、即時・無条件での恒久的停戦を求める決議案に、この期に及んでも反対しました。他の14カ国全てが賛成する中で、イスラエルを支持し、軍事的・経済的支援を続けるアメリカに、世界中から怒りの目が向けられています。
国連総会では、昨年、イスラエルの蛮行を止めるために、イスラエルへの制裁を求める決議が採択されています。また、パレスチナを独立国家として承認し、イスラエル・パレスチナの「2国家解決」という根本的な解決を求める決議も9月12日に採択されました。イスラエルがガザを占領しようとする、ヨルダン川西岸にどんどん入植していく、これを止めるために、パレスチナの国家承認をしようという、この新たな動きがどんどん広がっているんですね。
日本政府は、二つの国連決議に賛成しました。どちらも賛成したんです、制裁、国家承認。ところが岩屋(毅)外務大臣は19日、「パレスチナ国家承認」を見送ると表明しました。いままさに行われている国連総会でも、次々と国家承認が広がり、すでに150カ国以上、私の昨日の原稿は140になっていました。きょうの原稿は150カ国以上。アメリカの同盟国であるイギリス、フランス、カナダなども、新たに国家承認を行いました。もはや、国連加盟国の8割に達しています。それなのに、なぜ日本政府は背を向けるのか。アメリカの要請に屈服し従った、これ以外に説明がつきません。また日本政府は、イスラエルへの経済制裁どころか、イスラエルの軍需産業が参加する国際展示会「サイバーテック東京2025」を、経済産業省と内閣官房が後援しました。また防衛省では、ガザへの攻撃に現に使われているイスラエル製の攻撃型ドローンを購入する動きさえあります。なんと情けないことでしょうか。
トランプ大統領のアメリカに付き従い、世界からの信頼を失い、日本も孤立するこんな道を歩むわけにはいきません。日本共産党は、日本政府に、イスラエルへの制裁、パレスチナ国家承認を直ちにとあらためて要求します(拍手)。そして、アメリカに対して、毅然(きぜん)と、イスラエル支援をやめるよう働きかけることを求めるものです。この場からも、あらためて「イスラエルはジェノサイドを直ちにやめよ」「即時・無条件、恒久的停戦を」と、ともに求めようではありませんか。(大きな拍手)
アメリカいいなりの大軍拡は、戦争への道
アメリカいいなりの大軍拡の暴走が止まりません。
軍事費の異常な増額は、すでに3年連続、来年度はさらなる増額で9兆円を超える軍事費を防衛省は要求しています。その内容も、いよいよ外国を攻撃するミサイルの配備です。8月終わりには、長射程ミサイル配備の計画が、該当する自治体に何も知らされないままに発表され、住民や自治体から抗議の声が次々とあがっています。また、米軍の指揮・統制のもとに自衛隊を組み込む体制づくりが進められ、日米軍事演習は、日本が戦場となることや、アメリカの核使用まで想定した訓練へとエスカレートしています。
いまも、陸上自衛隊と米海兵隊による史上最大規模の共同訓練「レゾリュート・ドラゴン25」が行われていますが、自衛隊から1万4000人、米軍から5000人が参加し、全国で50カ所の施設を使用するとしています。21年は自衛隊1400人、米軍2650人、使われた施設は5カ所でしたから、まさに桁違いの訓練となります。その内容も過激化し、「多層的・統合的な火力投射能力を発揮する」として、アメリカの陸軍、海軍、海兵隊、そして日本の自衛隊の中射程・長射程ミサイルをこれでもかと日本各地に展開させるなど、日米一体で外国を攻めるという共同訓練になっています。
トランプ政権は、さらなるむちゃくちゃな大軍拡の要求も日本に突き付けています。「GDP比3・5%以上、年間21兆円」--いまでも年間7兆円から8兆円もの軍事費が、社会保障や教育の予算をおしつぶしているのに、21兆円もの大軍拡となったらどうなるのか。暮らしの予算への圧迫だけでなく、軍拡大増税がおこることは必至です。
国会では、大軍拡賛成の大合唱がさらに強まる危険性がありますが、トランプ大統領に黙って付き従うのか、21兆円もの大軍拡を受け入れるのか、日本政府はもちろん、すべての政党が態度を問われます。大軍拡に断固として立ち向かい、各地の基地強化、ミサイル配備、沖縄新基地建設に、住民のみなさんとともに立ち向かう--日本共産党の役割はますます大切になっています。
この大軍拡への転換点は、2015年の安保法制の制定です。それから10年の節目を迎えた9月19日、「安保法制廃止」を掲げる集会が各地で行われました。私は、国会前の集会で連帯のあいさつに立ちましたが、その中で、この日、朝日新聞に掲載された法学者・長谷部恭男早稲田大学教授の言葉を紹介しました。長谷部教授は10年前、自民党の推薦で憲法審査会の参考人となり、ところが自民党の期待を裏切って、「集団的自衛権行使容認は、憲法違反」と発言して、与党に激震が走った。このことを、みなさんも記憶しておられるのではないかと思います。長谷部教授は対談のなかで、「憲法9条は死文化した」という声に対して、次のように述べています--「憲法は生きている。憲法をくぐらずに合理的な安全保障政策を考えられるはずがない。大丈夫です。専守防衛というタガを締め直すための『護憲的改憲』を唱える人がいますが、それが『壊憲的改憲』につながるリスクをまったく考慮していない」「タガがゆるんだら締め直す。ゆるませている政治家を交代させるのが正道です」(拍手)。憲法は生きている。日本が「専守防衛」を投げ出してよいのか、海外で米軍とともに戦争する自衛隊にしてしまってよいのか、これは、立場の違い、政党支持の違いを超えて、多くの国民がかかえる不安や疑問だと思います。こうした国民多数の声に正面から応えることができるのは、日米同盟絶対の政治から抜け出すという展望をもつ、私たち日本共産党だと確信します。(拍手)
大軍拡反対とともに、「安保法制廃止」「立憲主義の回復」を掲げ、アメリカいいなりの政治の転換を--この世論を国民多数のものにしていこうではありませんか。(大きな拍手)
3 極右・排外主義と正面からたたかい、人権の尊重を求める党
第3に、日本共産党は、極右・排外主義と正面からたたかい、人権の尊重を求める党です。
極右・排外主義と断固としてたたかい、本当の改革へ人々の結集を
参議院選挙で「日本人ファースト」を掲げた参政党が伸長し、いま、極右・排外主義の危険な流れが、日本の政治と社会に起きています。維新の会は、参政党に呼応するように、外国人問題での政策を発表しました。わざわざ「排外主義ではない」と書いてあるんですが、中身を読んでみたら、排外主義そのものでした。
犯罪や治安の悪化を外国人と結びつける、このこと自体が、深刻な差別と分断を生み出し、いま日本に暮らす外国の人たちに大きな不安をもたらしています。こうした主張を、政党や政治家が喧伝(けんでん)することによって、外国人への恐怖心や憎悪が広がり、あおられ、その結果、外国人やそのコミュニティーに危害がもたらされる危険性さえあります。すでに、外国籍の方が経営する店に対する嫌がらせ、あるいは外国人の子どもへの脅しなどの事態が起きていることは重大です。排外主義の主張が、どれほど危険か、すべての政党・政治家は、自覚すべきではないでしょうか。(拍手)
日本共産党は、差別・排外主義と断固としてたたかいます。日本に暮らし、働き、学ぶすべての人の人権を尊重することを求めます。この立場は、戦前から一貫したものです。戦前、私たちの先輩は、侵略戦争に反対するとともに、植民地支配に反対し、その解放を求めてたたかい続けました。朝鮮半島や台湾出身の在日外国人への差別や人権侵害にも立ち向かいました。この歴史にも立って、差別・排外主義を克服するために力をつくすことを、あらためて表明するものです。(拍手)
新自由主義の破綻の反動的あらわれ
極右・排外主義が台頭してきた大きな根ともいえるものは、新自由主義の行き詰まりと破綻です。欧米諸国でも、日本でも、弱肉強食と自己責任を押し付ける新自由主義が吹き荒れ、それにもとづくグローバリゼーション=ヒト、モノ、カネ、情報、文化などが国境を超えて動くなかで、ごく一部の超富裕層と大企業に巨額の富が集中し、一方で、99%の人は貧しくなっていく。その時に、暮らしが苦しいのは「移民のせいだ」「外国人が優遇されている」というウソとデマが大量に流され、生活の不満をのみ込むようにしてこの潮流が台頭しています。
加えて、日本の極右・排外主義は、自民党の歴史逆行の姿勢・体質を土壌にして生まれてきたものです。侵略戦争と植民地支配の歴史をねじまげ、そして日本軍国主義を美化し、戦前の専制政治に時代を逆行させようという主張が際立っています。こうした社会的・経済的・歴史的な根っこをもつものですから、甘く見るわけにはいきません。私たちは、本腰をいれてたたかう決意です。(拍手)
排外主義に抗議する幅広い市民との連帯
参議院選挙で吹き荒れた外国人差別の主張に対して、日本ペンクラブが桐野夏生会長を先頭に、選挙期間中の7月15日に緊急会見を開き、「選挙活動に名を借りたデマに満ちた外国人への攻撃は私たちの社会を壊します」とする緊急声明を発表するなど、即座に、差別と排外主義への抗議の声が、市民の中から次々とあげられたことは、日本社会の民主主義の力を示すものであり、大きな希望です。選挙後も、弁護士、音楽プロデューサー、作家、ジャーナリストなど各界の有志のよびかけで、排外主義に抗議する街頭宣伝が行われ、野党の国会議員も駆けつけてスピーチしました。その後も、全国各地で市民のみなさんが、差別・排外主義に市民の連帯の力で立ち向かおうとアピールを繰り広げています。
新聞メディアも、参議院選挙中に、ファクトチェックの記事を掲載し、「社説」では、「外国人政策 排外主義の助長懸念する」(「毎日」7月12日付)、「『優先』と分断の先に 排外主義の台頭を許すな」(「朝日」7月13日付)、「外国人対策強化 差別の助長は許さない」(「東京」7月18日付)、「情報見極め民主主義を守る1票を」(「日経」7月20日付)などの主張が相次ぎました。
全国知事会も、参院選直後の7月23、24両日の総会で、「排他主義、排外主義を否定し、多文化共生社会を目指す我々47人の知事がこの場に集い、対話の中で日本の未来を拓(ひら)くに相応(ふさわ)しい舞台となった」とする「青森宣言」を全会一致で採択しました。また「国は外国人を『労働者』と見ているが、地方自治体から見れば日本人と同じ『生活者』であり『地域住民』である」と指摘して、国に政策や予算を要望する「提言」もまとめました。
私たちは、差別や排外主義に反対する幅広い方々との連帯を広げていきます。国民の理性と良識の力を結集して、危険な潮流を包囲することを心からよびかけるものです。(拍手)
欧州左翼政党の排外主義とのたたかいに学んで
日本共産党は、党として排外主義とどうたたかうのか--第6回中央委員会総会では、志位和夫議長が、ヨーロッパでの排外主義とのたたかいについて紹介する発言を行いました。これは、昨年、今年と2度にわたってヨーロッパの左派政党との交流を深める中でつかんだ経験です。とても大切だと私も実感しましたので、その一部を紹介したいと思います。
まずイギリスです。イギリスは、スターマー労働党政権が緊縮政策、あるいはパレスチナ対応でのイスラエル擁護、大軍拡を続けて国民の期待を裏切る状況が起きています。このもとで、極右政党リフォームUKが支持率で1位へと伸長しています。労働党前党首のジェレミー・コービン氏は、こうした流れに正面から対決して、11月に新しい政党を結成しようとしていますが、そのよびかけ文には、排外主義について次のように書かれています。「分断をあおる者たちは、私たちの社会の問題は、移民や難民によって引き起こされていると考えさせようとしています。しかし、そうではありません。問題は、企業や億万長者の利益を守る経済システムによって引き起こされているのです」--この新しい党は「富と権力の大規模な再分配」を行うことを掲げ、すでに80万人を超える人々が賛同の署名を寄せているということです。
次にベルギーです。ベルギー労働党は、極右政党「フランダースの利益」と長期にわたり、ねばりづよくたたかっている政党です。排外主義と断固としてたたかう姿勢を貫いていることが、選挙での躍進の一つの重要な要因となっているということです。この党の欧州議会議員マルク・ボテンガ氏は、志位議長との会談で次のように述べています。「極右とたたかううえで魔法の処方箋、魔法のレシピはありません」「極右台頭の背景には人々の怒り、生活の苦しみ、物価が高いが給料が上がらないということがあり、それらの非難をイスラムや移民に向けています。治安やテロ問題もすべて彼らのせいにしています」「私たちの課題は二重です。一つは、有権者の怒りを正当だと認めることです。正当な理由があって怒っているわけで、それを認めることから出発しています。二つ目は、希望を語ることです。物事は変わる、社会は変えられることを訴えています」ということです。
そして最後はドイツです。ドイツ左翼党は、極右政党AfD(ドイツのための選択肢)が支持を大きく伸ばすもとで、昨年8月の選挙では重大な後退を喫しました。しかし今年2月の総選挙で躍進、昨年から今年で8万人の新たな党員を迎え入れました。AfDも引き続き議席を伸ばしていますので、まさに、せめぎ合いのたたかいです。ドイツ左翼党前議長・欧州議会議員のシルデワン氏は「極右に対する明確な態度」をとったことが躍進につながったと述べています。ドイツでは、メルツ党首のキリスト教民主同盟がAfDと結託して、今年1月、難民受け入れ制限決議案を採択したことが大問題となったのです。国民の中で、ファシズムと排外主義を許してはならない、この声がとっても広がった。そのときに、この国民の声に応えて、左翼党が連邦議会でメルツ首相を厳しく非難し「私たちが民主主義を守る防火壁だ」と訴えた--この動画が実に2900万回再生され、これが大きな転機となって、躍進につながっていったということです。
極右・排外主義の台頭は、社会にとって深刻な危機です。左翼進歩勢力が押し込まれてしまう局面もあります。しかし、この潮流の台頭に流されることなく、断固とした姿勢で、極右・排外主義とたたかい、本当の改革を求めて支配勢力とたたかうならば、危機はチャンスになりうることを、ヨーロッパの同志たちのたたかいは示しているのではないでしょうか。日本でもこのヨーロッパのたたかいに負けないたたかいをやろうではありませんか。(拍手)
政治を変えてほしいという「願いを共有」し、「希望を届ける」
参議院選挙後、参政党をなぜ支持したのかということを取材した報道をみると、日本でも、いまの生活の苦しさ、将来への不安から、自民党政治に怒り、政治を変えてほしいと願う声が多いことがわかります。このことをふまえて、私たちは、第6回中央委員会総会で、極右・排外主義を克服する最も根本的な道として、次の姿勢を打ち出しました。
「『この生活苦を何とかしてほしい』という『願いを共有』し、その原因は決して『外国人』にあるのではなく、自民党政治にあることを明らかにし、この政治を変えることにこそ解決の道があるという『希望を届ける』ことが大切である。極右・排外主義の『生みの親』も『育ての親』も自民党であり、自民党政治と正面からたたかい、この政治を変える展望を示すことにこそ、極右・排外主義を克服する最も根本的な道がある」
差別や排外主義を許さないという街頭からの訴えでも、この立場を貫いていきたいと思います。ここでは、ねばりづよい対話の努力が求められます。ちょうど1週間前、東京の錦糸町駅前で、日本共産党の街頭宣伝をやりました。街宣が終わってから、23歳だという男性が話しかけてきました。その男性は、私が演説後に、いろんな人と話をしているのを終えるまで、ずっと待っていたんです。「外国人を差別ではなく、区別することは必要ではないのか」とまず言われました。そして、“医療ただのり”とか、治安の悪化への不安とか、移民政策をとれば日本人が低賃金になるのではなど、フェイクを含んだ情報にもとづく話が続きました。私に反論したいというよりも、こういう自分の抱える不安を聞いてほしいという姿勢を感じました。あまりに時間が短くて、納得を得るというところまでは足らなかったんですが、最後に「日本共産党の政策も見てほしい。また私たちと話す機会をぜひ」と伝えると、「わかりました」というやりとりで別れました。
こういう対話のあと、私はベルギー労働党の活動を思い起こしました。さきほど紹介しなかった部分があるんですが、ベルギーの港湾労働者の多いアントワープ市では、極右政党が40%の支持率を得ていたといいます。そのもとで、ベルギー労働党は、10年、20年という時間をかけて、港湾の街、労働者街の家を一軒一軒訪問して要求を聞く、対話をする。たとえば「公営住宅に入れないのはスーダン人のお隣さんがいるからではなく、公営住宅が足りないことが問題なんですよ」と、こういう対話をひたすら重ねながら、極右政党とたたかって支持を得ていったといいます。「魔法のレシピはない」という言葉の意味がここにあるんですね。
私たちも、極右・排外主義の勢力がウソとデマで外国人への差別をあおっている事実を伝えつつ、いまの政治への怒りや、生活の苦しみに耳を傾け「共感する」、そして、苦しみや閉塞(へいそく)感が何によってもたらされたのか、どこに解決の方向があるのか、「希望を届ける」ところまで、ねばりづよい対話に挑戦する決意です。それは、手間もかかる活動でしょう。時間もかかるでしょう。けれど、この対話や働きかけに挑戦してこそ、極右・排外主義の勢力への支持を根本的に崩すことができるし、本当の改革、新しい政治への改革の側に、人々を結集していくことができるでしょう。それは、やりがいに満ちた仕事ではないでしょうか。そして、「希望を語る」のですから、前向きな明るい活動として、みなさんとともに挑戦したいと思います。(拍手)
ジェンダー平等への逆行――排外主義の大きな弱点
極右・排外主義の勢力は、その分断の刃(やいば)を外国人だけでなく、国民にも向けていきます。ヨーロッパでも、アメリカでも、そして日本でも、それはジェンダー平等に憎悪を向け、ジェンダー平等への大きな前進を逆行させようとする特徴をもっています。
しかし、この間、日本でも世界でもわき起こり広がっているジェンダー平等を求めるムーブメントを押し込め、黙らせることは絶対にできません。人間の尊重へと社会が前に進むことは、世界をみても歴史をみても、人類社会の発展方向そのものだということを、まず強調したいと思います。(拍手)
そして、彼らのジェンダー平等への攻撃は、極右・排外主義の政党が、新しい政党どころか、古い時代にしがみつく、人権を軽んずる勢力であるということを天下に知らしめています。
私もテレビの党首討論で、参政党の党首が、選択的夫婦別姓を導入したら、日本の治安を悪くすると主張したことに驚き、あきれました。司会者は、この発言で選択的夫婦別姓のテーマを終わらせようとしましたので、ここで黙るわけにはいかないと手を挙げて、「名前を変えずに結婚したいという人は現にいる。これはアイデンティティー、人権の問題だ」と一言でしたが発言をしました(拍手)。もっと言いたいことがある人はこの場にいると思います。
人権の問題をこれほど軽く扱う人たちに、ジェンダー平等の流れを阻むことなどできるはずがありません。排外主義は、外国人の問題だけではない、多様な生き方、多様な家族、個人の尊重への攻撃として、大きな連帯で、この動きを打ち破ろうではありませんか。ともにがんばりましょう。(拍手)
4 核兵器廃絶、平和の地域協力の構築へ、国際連帯を広げる党
第4に、日本共産党は、核兵器廃絶、平和の地域協力の構築へ、国際連帯を広げる党です。
核兵器廃絶へ――「核抑止」論を乗り越え、核兵器禁止条約を前へ進める
被爆80年の夏、原水爆禁止世界大会、そして広島市・長崎市での平和記念式典は、核兵器廃絶への国際連帯を広げる重要な場となりました。
8月5日、「核兵器廃絶日本NGO連絡会」と「核兵器をなくす日本キャンペーン」の共催で、各党国会議員が参加する討論会が行われ、被爆80年の節目を迎え、日本が果たすべき役割が議論されました。なお、すべての政党によびかけがあったのですが、参政党と保守党は不参加でした。この討論会で私は、日本が果たすべき役割は、被爆80年の今年、核兵器禁止条約の批准に向けて動くことだとまず述べて、そのためには「核抑止」論の克服が必要だと発言しました。4分ぐらいの短い発言です。
唯一の戦争被爆国である日本が核兵器禁止条約に参加すべきだ、あるいは締約国会議にオブザーバー参加すべきだ--これは、自民党をのぞく党の共通するスタンスで、今回の討論会でも、被爆80年に結局、3月の締約国会議に日本政府が参加しなかったことを批判する発言が相次ぎました。一方で、日本政府が「核抑止」論にしがみついていることが問題だと指摘して、その克服への具体的な議論をよびかけたのは私だけでした。
各党の発言に続いて、オーストリア外務省のアレクサンダー・クメント軍縮局長--この方は禁止条約の会議にすべてかかわっている方ですが、この方が、「核抑止」論の克服を発言の中で強調しました。また、核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)のメリッサ・パーク事務局長も「核の傘」への依存は持続可能ではない、と述べました。これも「核抑止」論への批判です。こういう発言を聞いていて、私は、この間の日本共産党の活動が、世界の核兵器廃絶の運動の発展と響き合っていることを実感しました。私は4分の発言の中に、何年にもわたる日本共産党の核兵器を巡る議論を凝縮させた、という思いがあるんですね。
この「核抑止」論の克服については、大切なので、少し丁寧にお話ししたいと思います。「核抑止」論は、核兵器廃絶に向けて、核兵器禁止条約への参加を広げるうえで、どうしても克服しなければならない課題です。日本政府も、自分たちは「核の傘」に入っているから、まさに「核抑止」の立場だから条約に入れないと言うわけですね。核兵器禁止条約は、ノーベル平和賞を受賞した被爆者のみなさんを先頭にした核兵器の非人道性の告発--絶対にあってはならない地獄を生み出す非人道性の告発、この「人道的アプローチ」が実を結んだものでした。そして、核兵器の非人道性を批判することと、いざとなったら核兵器の使用のボタンを押すことを前提とする「核抑止」論は決して両立するものではありません。「人道的アプローチ」は「核抑止」論を乗り越える大きな力です。
同時に、私たちが国会でこの問題を提起すると、「非人道性」というのは日本政府も認める。しかし、「安全保障環境が悪い」という言い訳を持ち出して、禁止条約に背を向ける、「核抑止」にしがみつく。「しかし安全保障の観点からも『核抑止』論は合理性をもつのでしょうか。核兵器禁止条約の第3回締約国会議の報告書は、『いかなる立場に立つ国であれ、核兵器は、すべての国家の安全に対する深刻かつ根本的な脅威』であると明記しました。この報告書が指摘しているように、『核抑止が失敗する可能性があるという事実には疑いの余地』はありません。『核抑止』は絶対のものじゃない。破綻する可能性がある。それは、かつてのキューバ危機をはじめ、あと一歩で人類の破滅をもたらした過去の歴史が証明していることです。いま、このことが国際会議のなかで議論されています。私たちが、いまこうして核戦争がおきずに存在しているこのこと自体が、幸運にすぎないのです」(フォーラム2での志位議長の発言から)。先ほど、私が響き合ったと思ったというオーストリアのクメントさんというのは、まさに「核抑止」で安全を守るというのは仮定の話でしかないと強調されたんです。
広島市・長崎市の平和記念式典での平和宣言、県知事や国連事務総長のあいさつなどを聞いていても、石破首相以外は、核兵器禁止条約への参加が核兵器廃絶への道だという立場を明確に示していました。広島県知事からは、「核抑止」論を正面から批判する言葉もありました。感銘を受けました。
私たちは世界の本流を前へと動かしている--このことを大きな確信として、「核抑止」論を克服しましょう。核兵器禁止条約の批准、来年の第1回再検討会議への日本政府の参加を求めようではありませんか。(拍手)
ユーラシア大陸の東西での欧州議員との連帯
原水爆禁止世界大会を舞台に、ヨーロッパとの国際連帯が発展したことも大きな成果です。今年の原水爆禁止世界大会では、二つのフォーラムが開催され、フォーラム2では、先ほど排外主義とのたたかいで紹介したイギリス、ベルギー、ドイツの国会議員、さらにアメリカの代表、そして日本から志位和夫議長・衆議院議員という、核兵器保有国とその核の傘のもとにある五つの国の代表が意見を交わし、連帯を確認することができました。
「核抑止」論を克服して、核兵器禁止条約に参加するというのは、この五つの国にとって共通の課題で、これを実現することは、核兵器廃絶へと世界を大きく動かすことになります。アメリカとの軍事同盟強化と大軍拡が急速に進められていることも、ヨーロッパと日本の共通した問題です。ヨーロッパでは、ロシアのウクライナ侵略によって、大軍拡を当然とする世論が日本よりもはるかに強いなかで、左派政党が、大軍拡に反対の立場を貫いていることは、私たちに大きな勇気を与えてくれます。ユーラシア大陸の東西で進む大軍拡に対して、ユーラシア大陸の東西で連帯して、大軍拡反対、平和の国際秩序を求める--ここに、世界の希望があるのではないでしょうか。(拍手)
ヨーロッパとの平和の連帯の最後に、私の小さなエピソードを紹介します。
8月6日、原水爆禁止世界大会ヒロシマデー集会で、連帯のあいさつを終えたとき、舞台袖でスピーチの順序を待つイギリスのコービン氏と言葉を交わすことができました。私にはどうしてもコービン氏に伝えたいことがありました。
大学2年、19歳のとき、「赤旗」に報じられたイギリスのCND(核軍縮運動)の大規模なデモの写真に衝撃を受け、励まされた。このことを伝えたかったんです。ヨーロッパの運動と呼応する日本共産党に、この運動を知って入党したのだと。これらのことを通訳の方に伝えてもらいました。コービン氏は満面の笑みで、「私は14歳でCNDに加わった。いまも活動している」と答えました。コービン氏がCNDに加わったのは、60年代の「キューバ危機」といわれる核戦争の危機の時です。私は80年代の米ソ核軍拡競争の時代に、民青同盟の核兵器廃絶の運動に加わり、CNDに勇気づけられました。ヨーロッパのこの大規模な運動を知ってほしくて、大学のキャンパスにCNDなど海外の反核ポスターを掲示したこともありました。
私たちの国際連帯は、国境も時代も超えて紡がれ、確実に世界を動かしている--この確信をみなさんに伝えたいと思います。(拍手)
東南アジア、欧州、そして北東アジアでの対話――「東アジア平和提言」を力に
私たちは、昨年4月に発表した「東アジア平和提言」を大きな力にして、平和の国際連帯をさらに発展させています。
この「提言」を提唱する力となったのは、2023年12月のASEAN(東南アジア諸国連合)3カ国--インドネシア、ラオス、ベトナムへの日本共産党代表団の訪問でした。私も参加し、ASEANのねばりづよい対話の努力、年間1500回もの会合に驚き、米中対立が強まるもとでも、アメリカの側にも中国の側にもつかない、自主独立と中立という立場を堅持していることに感動し、時間がかかっても対話によってコンセンサス(合意)をつくることが大切、外交に勝者や敗者があってはならないという指摘に、深く考えさせられました。また、北東アジアでは“良い対話”の習慣がつくられていない、その要因として歴史認識など日本に関わる問題があるということを率直に指摘する意見をお聞きして、日本の政党である私たちの独自の責務を痛感しました。
ASEAN訪問を踏まえて提唱した「東アジア平和提言」は、(1)「ASEANと協力して東アジア規模での平和の地域協力の枠組みを発展させる」、(2)「北東アジアの諸問題の外交的解決をはかり、東アジア平和共同体をめざす」、(3)「ガザ危機とウクライナ侵略--国連憲章・国際法にもとづく解決を」という、世界の戦争と平和の問題を包括的にとらえ、現実の課題をどうやって前向きに打開していくのかを示した豊かな外交提言となりました。この「提言」を手に、ヨーロッパ、そして北東アジアへと、私たちの平和外交は発展しています。
欧州――ドイツでの国際会議と左派政党との対話
昨年8月31日、ドイツの進歩的シンクタンク、ローザ・ルクセンブルク財団が主催した国際平和会議「今こそ外交を!」に志位議長が招待され、「提言」の立場で発言・交流したことは、ヨーロッパとの新たな国際連帯への重要な契機となりました。
ロシアによるウクライナ戦争をどう終わらせるのか--国連憲章・国際法、ロシアを非難し即時撤退を求める4回にわたる国連決議にもとづいた「公正な和平」をなど、わが党の提起は、会議の趣旨と響き合うものでした。わが党が強調した「公正な和平」という主張は、いまウクライナ侵略を終わらせるうえで、停戦と和平をどういう立場で進めるかという点でも、いよいよ重要になっています。
また、このときにヨーロッパのみなさんが、わが党が提案、紹介したASEANの平和構築の努力にまとまってふれて、この国際会議の「よびかけ文」に、「新たなブロック対立を防ぐ」という一文が修正・補強されたことは、ブロック対立に反対し、包摂的な平和の枠組みをよびかけた「提言」が広く世界に通用する生命力をもっていることを示したものとなりました。
この会議に参加者であったコービン氏との出会いと交流、その後のドイツ、ベルギー、フランスでの左派政党や労働組合などとの会談が、その後の国際連帯へと発展していることも強調したいと思います。
北東アジア――中国、韓国の政府との対話
北東アジアはどうか。今年4月、日中友好議員連盟の中国訪問に、日本共産党から志位議長が参加し、中国の要人との三つの会談すべてで発言し、中国の党と政府の中枢に、「提言」の内容を直接伝えることができました。日中両国は「互いに脅威とならない」という2008年の両国首脳の合意にもとづいて行動すべきなどの内容を直接伝え、中国側からも「日本共産党の提言を重視している」という発言があったことは重要です。また、「東シナ海などでの力を背景にした現状変更の動きを自制してほしい」「台湾問題の平和的解決を強く願っている。日本共産党は中国の武力による威嚇や行使に反対する。同時に、第三国による軍事的関与や介入に反対する」と、わが国にとって焦点となる懸案についても、わが党は率直に意見を伝えました。
中国に対して、言うべきことはきっぱり言いつつ、両国関係を前に動かすために力をつくす--こうした外交こそ、本来、日本政府が責任をもって行うべきではないでしょうか。(拍手)
今年は戦後80年の節目の年です。とくに、北東アジア諸国との外交では、歴史問題への対応が深い意味をもってきます。8月24日、韓国の李在明(イジェミョン)大統領と、日韓議員連盟との会談にやはり志位議長が参加し、大変短い時間のなかでも「提言」の重要な内容を伝えることができました。
李大統領は、「(日韓両国には)難しい問題もあるが、相手の立場を理解し、配慮していくことが、協力関係を確かなものにしていくことになると確信しています」と言われた。かなりオブラートに包んで言っているんですね。これを受けて志位議長は、「それこそが日韓両国の友好関係を発展させる一番のカギだと思います」と述べたうえで、「戦後80年にあたって、日韓両国の友好関係をさらに発展させていくためには、1990年代の三つの重要文書--村山談話(95年)、河野談話(93年)、および日韓共同宣言(98年)の核心的内容を今日に引き継ぐことが大切だと考えます。日韓両国間の二つの懸案については、被害者の名誉と尊厳の回復が何よりも大切であり、そのために日本政府は誠意ある対応を行うことが重要です」と発言しました。非常に緊張が走る中で発言したと。
これは「提言」のなかで、「歴史問題の解決--戦後80年にあたって日本がとるべき基本姿勢」の内容をふまえた発言です。侵略と植民地支配を国策の誤りと認めて反省を示した「村山談話」、日本軍「慰安婦」問題について、軍の関与と強制性を認めて反省を表明した「河野談話」、韓国に対する植民地支配への反省を表明した「日韓共同宣言」、これらの核心的内容を歴史問題に対する日本政府の到達点として継承すべきだということです。そして、この立場で、日本軍「慰安婦」、徴用工の問題は、被害者の名誉と尊厳の回復をはかることが大切だという、私たちの党の意見を伝えた。これは全部伝わっていると思います。
志位議長の発言を受けて、李大統領も歴史認識について述べて、この問題が前向きに解決されていくことは、韓日両国民にとっても、アジアの平和にとっても良いことだと強調し、「(韓国と日本は)本当の友人、本当の兄弟になりたいと願っています」と語ったということです。
侵略戦争と植民地支配に命がけで反対し、いまも日本軍国主義の美化を許さず、大軍拡にも断固として反対する日本共産党の存在そのものが、北東アジアの平和構築への希望であるということも強調したいと思います。(拍手)
北東アジアでの問題の解決は、戦争の心配のない東アジアをつくるうえで、最も中心的な課題です。これを大切な一歩として、さらに「提言」を手に、私たちの外交努力を発展させたいと思います。
5 資本主義がもたらす害悪とたたかい、未来社会の展望をもつ党
第5に、日本共産党は、資本主義の「利潤第一主義」がもたらす害悪とたたかい、未来社会の展望をもつ党です。共産党という名前にもつながる、日本共産党の根源的な魅力がここにあると思います。
資本主義がもたらす害悪として、深刻化の一途をたどる気候危機の問題を指摘しなければなりません。最高気温35度を超える猛暑、頻発する豪雨、そして竜巻など、日本でも気候危機は、命と暮らし、農業や漁業などの産業を脅かすところまで来ています。産業革命以降の資本主義の経済活動によって、地球温暖化が止まらない、直ちに対策を強めなければ地球環境の悪化が加速度的に進んでしまう--いま私たちは、人類の生存にも関わる深刻な事態に直面しています。
日本共産党は、科学者や専門家のみなさんの意見や取り組みに学び、省エネ・再エネへの抜本的なシステムチェンジを求める「気候危機打開2030戦略」を打ち出して、さらに2035年までの対策を求める政策へと発展させています。そして、石炭火力発電にしがみつき、原発新増設を行い、大企業の利益を最優先にして、気候危機にまともに向き合わない自民党政治の転換を訴えています。
この問題は、一刻の猶予も許されない問題であり、資本主義の枠内でも解決のための最大の努力が必要です。同時に、資本主義というシステムをこのまま続けていいのかが、人類にいま鋭く問われています。
資本主義を乗り越えた先の社会--未来社会への展望を語ることが、こんなに大切なときはありません。ただ、社会主義・共産主義には「自由がない」というイメージが、国民の中に根強くあることも事実です。このもとで、私たちは、第29回党大会決定で、「わが党綱領が明らかにしている社会主義・共産主義の社会は、資本主義社会がかかえる諸矛盾を乗り越え、『人間の自由』があらゆる意味で豊かに保障され開花する社会である。『人間の自由』こそ社会主義・共産主義の目的であり、最大の特質である」と、未来社会への展望を豊かに発展させました。この大会決定は、党内外で大きく歓迎されています。
気候変動への危機感や、格差と貧困の問題から、資本主義への矛盾を感じている若者は決して少なくありません。しかし同時に、社会主義・共産主義は、かつてのソ連のように自由がない社会ではとも思っている。党大会決定が、マルクスに立ち戻って、「人間の自由」こそが社会主義・共産主義の目的だと解明したことで、未来社会への希望が大きく切り拓かれた--「人間の自由」という未来社会論に感動して、日本共産党に入党したい、私は共産主義をめざしたいんだと、こういう若者たちも次々と生まれています。
『資本論』を導きに、未来社会への展望を語る
この大会決定の実践として、昨年と今年、志位和夫議長が、民青同盟主催のオンラインゼミで2回にわたって講演を行い、それぞれ本となって刊行されました。
昨年刊行されたのが、この『Q&A 共産主義と自由』(青本、新日本出版社)です。「資本主義はほんとうに自由を保障しているのか」という問いかけからはじめて、大会決定が解明した、「利潤第一主義からの自由」「人間の自由で全面的な発展」「発達した資本主義国の巨大な可能性」という三つの角度から、社会主義・共産主義の特質を詳しく述べたものです。資本主義的な搾取によって奪われているのはモノやカネだけではない、搾取をなくすことで労働時間がグッと短縮されて、すべての人が十分な「自由な時間」を得ることができる、それが「人間の自由で全面的な発展」を保障するカギであり、「自由な時間」こそが真の富だ--こうしたマルクスの探究の過程を『資本論』を導きにして解明したことが、衝撃的に受け止められています。「自由な時間」というキーワードは、「働いて、食べて、寝るだけの人生で良いのか」「豊かな人生とは何か」を問いかけるものとなり、労働時間短縮のたたかいを励ます力となっています。
そして、今年、『Q&A いま「資本論」がおもしろい』(赤本、新日本出版社)が刊行されました。この本では、「資本主義的搾取」が正面から論じられています。そもそも搾取とは何か、労働者はどのように搾取されているのか、搾取がどのように拡大され、それが社会をどう変え、労働者階級にどういう運命をもたらすか、そして社会の変革はどうしておこるのかなど、『資本論』第一部での解明の「ごくごくあらまし」を、わかりやすく説明するとともに、『資本論』がどのような本なのかを明らかにしています。そして、『資本論』を読んでみようというきっかけにしてほしいとよびかけています。
この「赤本」では、「はじめに」の一節で、『資本論』について、次のように述べています。「資本主義という社会体制が、永久に続くものではなく、その胎内で成長した諸矛盾によって、次の体制--社会主義・共産主義に発展することを明らかにした書です。だからこの著作は、単に、資本主義経済を解説した本ではありません。『労働者と人民に社会を変えるたたかいを呼びかけた書』。ここにこそ、『変革』の書としての『資本論』の真髄があり、講演ではこの真髄を伝えたい。これが私の思いでした」。ぜひ読んでみていただきたいと思います。
私も、この「赤本」「青本」を読み、これが刺激になってもう一度『資本論』を読み直しているところです。『資本論』の中でも読みやすいのが「労働日」という章ですが、子どもたちの過酷な労働、狭いホコリだらけの部屋で服を仕立てる女性労働者の過労死などが、工場監督官の報告書を使って徹底的に告発されていて、マルクスが怒りをたぎらせながら書いていることが、ビンビンと伝わってきます。ここはスッと読めるという章ですよね。他は一文を読むだけで悪戦苦闘することもありますが。
「赤本」でもそのことを紹介していますが、特に次の言葉が胸にささりました。
「ここで強調したいのでは、マルクスは、労働者階級を、資本家階級によって搾取され、抑圧される、惨めな被害者としてだけ描いたのではないということです」「労働者階級が、搾取や抑圧とたたかうなかで、社会を変革する主体として、主人公として、どのように成長し、発展していくのかが力強く描かれています」、こういう言葉です。
労働者階級がたたかいのなかで自らの成長、発展をかちとることこそが、資本主義社会を終わりにして次の社会--社会主義・共産主義をつくる最大の原動力になる。ここにこそ、社会を変革する力がある。私も胸が熱くなる思いです。
いま、私たちは、「赤本」「青本」の内容を街頭からも伝えて、資本主義の矛盾、未来社会への展望を、対話のなかで語るということにも挑戦しています。
1週間前の16日、党本部のメンバーとともに、私も錦糸町駅前での対話街宣を行いました。「搾取はあると思う?」というシールアンケートが入り口です。「ある」「ない」にシールを貼ってもらうのですが、搾取は「ある」と答える人が多い、これが印象的でした。
「ない」と答えた人でも、これは私が対話した人ですが、「いま給料を上げてほしいですか」と聞くと、「自分は時給で働いている。時給が安すぎる、もっと上げてほしい」という答えが返ってくるんですね。また、税金や社会保険料を「国に搾取されている」という人もいました。多くの人が「搾取」ということを感覚的に感じている、これはとても大切だと実感しました。
同時に、この対話は私たちにとっても、相手の方にとっても、とても刺激的で面白いということもわかりました。本部のメンバーが、タイムカードを押すタイミングはと聞くと、「着替えた後だ」と答える。それは時給を「ちょろまかし」されているよと、食事の時間まで「ちょろまかし」されていると、この中に書いてあるよと。こんな対話になる。また、書店でも『資本論』に関する本があるので、『資本論』を読んでみたいという学生と私も対話をして、資本主義は発展するなかで、同時に没落を準備している、そういう観点で『資本論』を解説しているのが、この「赤本」なんですというと、パラパラと読んで、その場で購入していただきました。こういう対話が、あちらでもこちらでもとなりました。そして、1時間ほどで、準備した10冊は完売となりました。(拍手)
ぜひ多くの方に、「赤本」を読んでいただいて『資本論』を知ってほしいし、日本でも『資本論』を読むムーブメントを起こしたいと決意しているところです。
私たちには、日々、資本主義がもたらす害悪が降り注いでいます。生活の苦しみ、地球環境の悪化、生きにくさ、現実の厳しさに絶望的になったり、世の中が良くなる希望が見えなくなる時もあります。
だからこそ、マルクスが込めた熱いメッセージ、抑圧された労働者・人民のたたかいによってこそ、社会は変えられる、この希望をみんなのものにしていきたい。「赤本」と「青本」、そして『資本論』を力にして、こうした世の中を変えていこうという自覚的な連帯・団結を広げていくことを心からよびかけるものです。(拍手)
五つの点から、日本共産党の自己紹介をしました。最後に、私にとって、日本共産党がどういう党かを一言お話しして、講演を終わりたいと思います。
私にとって、日本共産党は「あきらめない生き方」そのものです。そして、「どんな困難も連帯の力で乗り越える」ことを教えてくれる場です。
日本の政治の歴史的岐路にあって、私たち日本共産党は、どんな困難があっても、どんな妨害があっても、自民党政治を終わらせて新しい政治への希望を拓くことを、決してあきらめません。それは、自民党政治を担ってきた支配勢力とのたたかいであり、国民の不満を取り込もうとする極右・排外主義とのたたかいでもあります。このたたかいに打ち勝って、どうしても次の選挙では勝利したい、それは、日本の夜明けを切り拓く、私たちの責務だからです。
いま、日本の政治や社会がこれからどうなるのかと、不安を抱く方がおられるでしょう。差別や分断が広がることに、怒りを抑えられない方もおられるでしょう。日本共産党にもっと大きくなってほしいと願ってくださる方も、大勢おられると思います。
そういうみなさんに、心からよびかけます。どうか、日本共産党に入党してください。
戦争か平和か、暗黒の政治か希望への変革かが問われるいま、ともに学び、たたかい、連帯を広げる道を、堂々と朗らかに歩もうではありませんか。心からよびかけまして、講演を終わります。ありがとうございました。(大きな拍手)