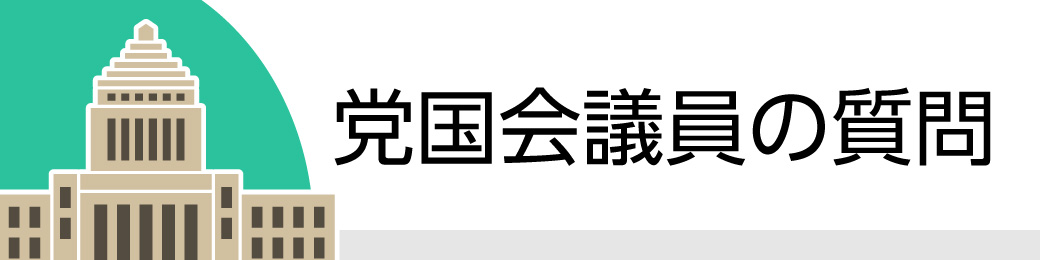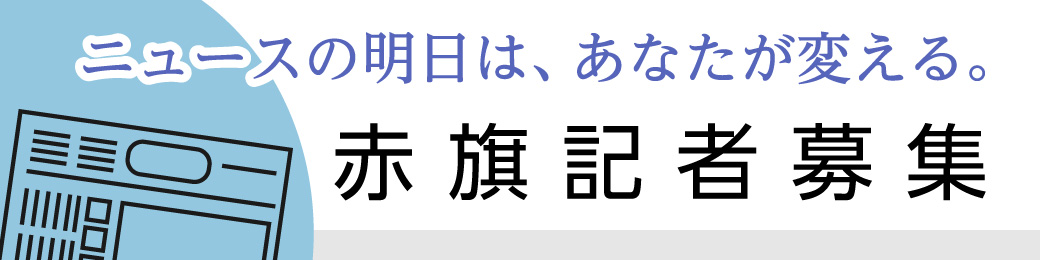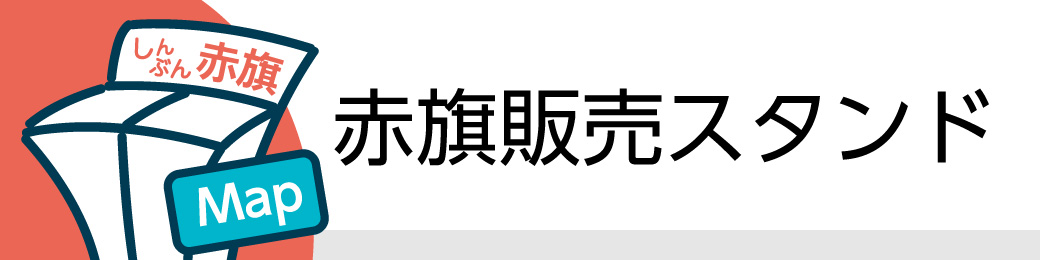2025年8月1日(金)
『資本論』を読むムーブメントを日本でも起こしたい
『Q&A いま「資本論」がおもしろい』志位議長の会見から
日本共産党の志位和夫議長が30日、『Q&A いま「資本論」がおもしろい』出版会見で行った発言を紹介します。
8月6日に『いま「資本論」がおもしろい--マルクスとともに現代と未来を科学する』という本を出版します。この本には、5月10日に、日本民主青年同盟主催でとりくまれた「学生オンラインゼミ・第4弾」で行った講演を、加筆・修正して収録しています。
この本の出版に込めた私の思いは、一言でいって、この本も一つの材料にしていただいて、“『資本論』を読むムーブメントを日本でも起こしたい”ということにあります。
「私たちは第4次マルクス・ブームを生きている」(米国から)

(写真)『Q&A いま「資本論」がおもしろい』の出版記者会見する志位和夫議長=30日、衆院第1議員会館
|
いまヨーロッパでもアメリカでも、マルクス『資本論』への新しい注目が広がり、読んでみようという動きが起こっています。
昨年、ヨーロッパを訪問したさいに、フランス労働総同盟(CGT)のみなさんと対談する機会がありました。労働時間短縮をめぐってつっこんだ意見交換をしました。そのときに、フランスの仲間たちから、「労働組合として学校をつくり、『資本論』の学習会を行い、労働時間短縮や『自由な時間』の拡大の意義を『資本論』から学んでいます」という話が出まして、大変、印象深く聞きました。
アメリカでは昨年9月に、ほぼ50年ぶりに、『資本論』第1部の新しい英語版が、プリンストン大学出版会から刊行されました。それを契機にして、進歩派の政治家--バーニー・サンダース上院議員を支持する人々の間で、『資本論』の読書会を組織する運動が全国的に広がっていることを聞きました。
最近、手に入れたのですが、イリノイ大学教授のアンドリュー・ハートマン氏が、『アメリカにおけるカール・マルクス』(2025年5月)という著作を出版しています。彼はこの本のなかで、「私たちは第4次マルクス・ブームを生きている」ということを言っています。「米国の歴史には多くのアメリカ人がマルクスを好意的に読んでいた時期が4度ある」というのです。1回目は19世紀後半、2回目は「大恐慌」が起こった1930年代、3回目は公民権運動とベトナム反戦運動が起こった60年代、そして4回目は今日だというのです。2008年のリーマン・ショックに始まり、ウォールストリート占拠運動、サンダース氏の選挙キャンペーンなどを契機にして、マルクスを読む人、読書会などが急増しているということを、述べています。
『アメリカにおけるカール・マルクス』のなかで、彼はこのように言っています。
「長い間、自由という概念に取りつかれていたこの国で、なぜ多くのアメリカ人が相対的に不自由だったのか? 生命、自由、幸福の追求を建国理念とする国家において、なぜこれほど多くのアメリカ人が見捨てられているのか。マルクスは、深く感じられる搾取の感覚を言葉にすることで、こうした不可解な疑問に対する説得力のある答えを長い間提示してきた。……マルクスがアメリカ人の生活に浸透したのは、彼が力強い自由論を提示したからであり、それはもう一つのアメリカの未来を示す地図でもあったからだ」
とても印象深い一文です。
「変革と希望の書」--「社会は変わるし、変えられる」
それでは日本ではどうでしょうか。なぜこんなにも暮らしが苦しいのか? なぜ一握りの超富裕層がますます富み、大多数の国民の賃金は押し下げられたままなのか? 長時間労働や非正規ワーカーの拡大など、人間らしい働き方が壊されているのはなぜなのか? 年々深刻になる気候危機はどうして引き起こされ、なかなか解決しないのか?
日本でも、多くの人々がその答えを求めている問題、たくさんの問いがあると思うのですが、それらの問題を根底から解くカギが、『資本論』のなかにあります。この書は、人間にとっての本当の自由とは何か、どうしたらそれが得られるかをあきらかにした書であり、そのためのたたかいを呼びかけた書であり、一言で言えば、「変革と希望の書」が『資本論』だと私は思います。
こうした状況のなかで、『資本論』を読むムーブメントを日本でも起こしたい。社会への深い閉塞(へいそく)感を感じている多くの人々に、「社会は変わるし、変えられる」という希望を広げたい。そうした思いでこの本をまとめました。
『Q&A 共産主義と自由』(「青い本」)とセットで読んでほしい
昨年出版した『Q&A 共産主義と自由』(「青い本」)との関係について一言、お話ししておきたいと思います。
「青い本」は、人間の自由と社会主義・共産主義の関係について、『資本論』を導きにして論じたものです。今回の「赤い本」(『Q&A いま「資本論」がおもしろい』)は、『資本論』そのものを、第一部にかぎって、「ごくごくのあらまし」ですが、論じたものです。「赤い本」は、「青い本」の、いわば理論的な土台を提供しているという関係になっています。
たとえば、「青い本」では、資本主義的な搾取によって、奪われているのは「カネ」や「モノ」だけでなく、「自由な時間」が奪われていることを話しましたが、資本主義的な搾取がどうやって起こるかのメカニズムについては、実はお話ししていないのです。今度の「赤い本」では、資本主義的な搾取の仕組み、さらに搾取がどのように拡大され、労働者や社会に何をもたらすかを『資本論』にそくして明らかにしています。ですから、この「青い本」と「赤い本」をセットでお読みいただければ、というのが私の願いであります。
記者団との一問一答
志位和夫議長が30日の『Q&A いま「資本論」がおもしろい--マルクスとともに現代と未来を科学する』出版発表記者会見で行った記者団との一問一答は次のとおりです。
「社会的ルール」をつくる民主的改革、その先に搾取制度の変革を
--『資本論』から得るエッセンスを、今の政治状況に置き換えたときに、どういう政策を打ち出していくことが有効だと考えますか。
志位 なぜ、こんなに生活が苦しいか。その直接の答えは、「新自由主義」の政策という問題があります。大企業の目先の利益を最優先させて弱肉強食を徹底する政策が、1980年代以降、世界でも日本でも押し付けられてきた。「新自由主義」から脱却し、暮らしと権利を守る「社会的ルール」をつくる民主的改革を訴えていきたい。
同時に、根源にあるのは資本主義的搾取です。冒頭に紹介したハートマン氏の本で印象深かったのは、「マルクスは深く感じられる搾取の感覚を言葉にすることで説得力がある答えを提示した」と述べていることです。労働者は懸命に働いても賃金は上がらない。一方で、超富裕層の資産は天文学的に増えている。多くの人々が「搾取の感覚」を感じています。それを「言葉」にした--その仕組みを人類で初めて解明したのがマルクスなのです。
賃上げ、労働時間短縮、非正規ワーカーの権利保障と正規化を進めることなどが緊急の課題ですが、同時に、それらをやりとげた先には、搾取制度そのものを変革することが大きな課題になってくる。こうした展望も大いに語っていきたいと考えています。
「賃上げとともに時短を」の課題について
--賃上げと同時に、「自分の時間をもっと確保していく」というのは、『資本論』から得るテーマになるのでしょうか。
志位 そう思っています。何よりもそれは切実な要求です。賃上げはもちろん急務ですが、それだけでは労働者の本当に豊かな生活は保障されません。「ただ働いて食べて寝るだけ」という生活は本当に豊かとはいえません。賃上げと一体に、「自由に使える時間」をみんなが持てるようにする改革が必要になります。
ただ、賃上げと時短を両方進めるのは難しさもあります。昨年、欧州を訪問した際に聞いた話では、フランスでは35時間労働制を導入した時に、新たな雇用が創出された一方で、多くの部門で賃金低迷を招いたということもあったそうです。次は32時間労働制に向けて、賃上げと時短を両立させる法的枠組みをつくるために頑張っているという話を聞きました。両方を追求していくことが大切です。
『資本論』の中心点が伝われば、世の中は大きく変わる
--どういった方々を対象に読んでいただきたいのでしょうか。
志位 日本の国民のみなさんに読んでいただきたい。とりわけ、若いみなさん、労働者のみなさんに読んでいただきたい。政党支持の違いを超えて、広い方々に読んでいただきたいと思っています。『資本論』の中心点が、国民全体、とくに労働者や若いみなさんの中に広がっていくことになれば、世の中は大きく変わります。そういう力を持っているのが『資本論』という著作だと思います。
教育、ジェンダー、環境--現代に響く新鮮な解明が
--とりわけ若い人に『資本論』の魅力をどのように伝えていくのでしょうか。
志位 マルクスは『資本論』で、資本主義社会を「肯定的理解」と「必然的な没落の理解」の両面で捉えました。マルクスといえば「資本主義反対の人」と思うかもしれないけど、そうじゃない。資本主義に対する厳しい批判とともに、この制度が人類社会においてどういう積極的意義を持っているのか、未来社会を準備するどういう要素をつくりだすのかなどについても、『資本論』では縦横に明らかにしているのです。
たとえば、『資本論』の「機械と大工業」(第13章)では、機械制大工業によって未来社会の要素が生まれてくることが、いろいろな形で豊かに語られています。
工場制度から「未来の教育」の萌芽が芽生えてくること、「未来の教育」の役割は「全面的に発達した人間をつくる」ことにあるという、「人格の完成」という今日の教育の目的に直結する命題が、出てきます。
ジェンダーの問題では、大工業によって、父親を中心とした「古い家族制度」が解体され、男女同権の基礎をつくりだすという考え方が述べられています。もちろん「ジェンダー」という言葉は使われていませんが、現代に響く新鮮な解明です。
さらに環境問題です。マルクスの時代は地球的規模での環境破壊は問題にならなかったけれども、資本主義的農業における農地の破壊に早くも着目して「物質代謝の攪乱(かくらん)」という言い方で告発し、それが未来社会で「再建」されるという展望を論じています。
これらは、現代に直接つながるものとして、若い方々も身近に感じられるのではないでしょうか。この本でも重視して紹介しました。
「新しいものを学ぼう」「自分の頭で考えよう」
--参院選では短いキャッチフレーズがうけました。そういう状況にどう立ち向かっていくのかお聞かせください。
志位 この本の最後に紹介したのですが、「新しいものを学ぼう」「自分の頭で考えよう」というメッセージをマルクスは述べています。その大切さを伝えていきたい。
もちろん、ワンフレーズで伝わるキャッチフレーズは大切です。同時に、世の中というのはワンフレーズでは表現できない複雑さと豊かさを持っているということも伝えたいのです。とくに資本主義社会は、さまざまな社会の仕組みが陰に隠されてしまうという特徴があります。たとえば、ひどい搾取がやられているのに、目には見えにくい。それを理解するには、科学の力で社会の仕組みを解き明かすことが必要ですし、その成果を粘り強く学ぶことが必要になります。「新しいものを学ぼう」「自分の頭で考えよう」というマルクスのメッセージを多くの若い方々に伝えたいです。
極右・排外主義の克服のために--「希望」を語ることの重要性
志位 いま起きている極右・排外主義の逆流について述べたいと思います。これは日本だけでなく、欧州でも米国でも起こっている。そこには相違点もありますが、共通点もあります。
この逆流は、一言で言って、資本主義の末期的な行き詰まり、とくに「新自由主義」とそれにもとづく「グローバリゼーション」の失敗の反動的な表現だと思います。1929年の「大恐慌」を境に、「ケインズ主義」が資本主義経済の指導理論とされました。それが1970年代の世界恐慌などで通用しなくなり、1980年代ごろから「新自由主義」が世界と日本を席巻します。しかし、貧困と格差の途方もない拡大を招くなど、いまや破綻は明らかになりました。それに対する不満、批判が、極右・排外主義に一つの「出口」を求めようとしているのです。
ですから、この逆流を克服するには、それがいかに危険かという批判が重要ですが、同時に「希望」を語ることが必要です。この暮らしの苦しさを打開する「希望」はある。それを政策の面でも、理念の面でも、いかに説得力をもって語るかが大切です。「新自由主義」に代わる希望ある民主的対案を語るとともに、資本主義そのものを根底から変えようじゃないかというムーブメントを起こし、希望ある未来を示していくことが必要です。『資本論』はこの点でも大きな力を発揮すると確信しています。