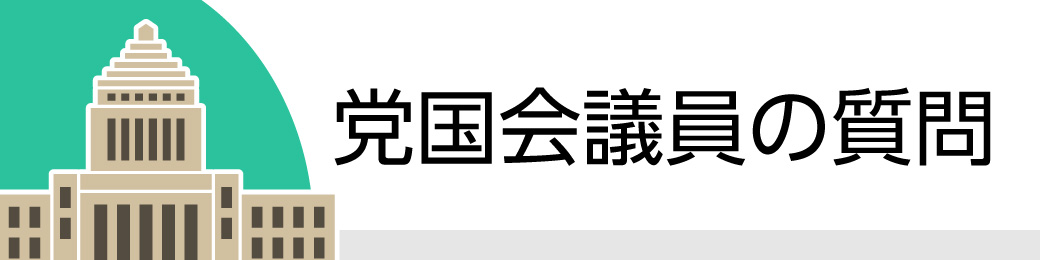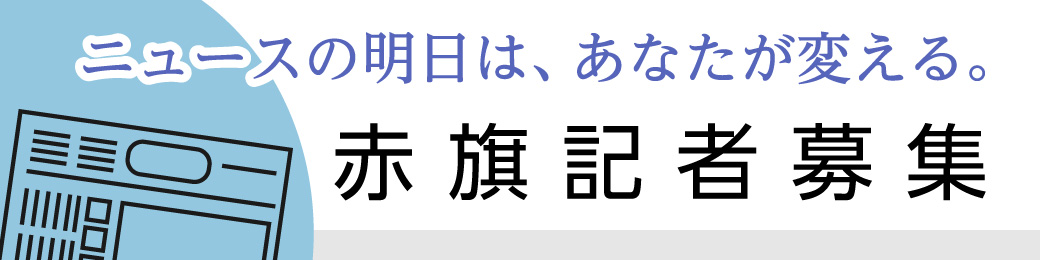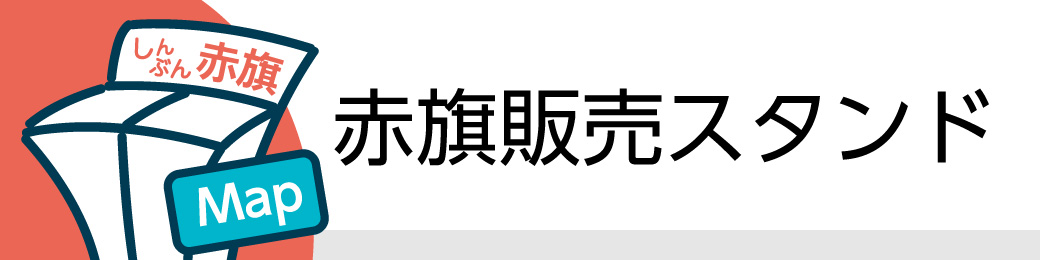2025年7月28日(月)
地域経済支える仕組みを 横の連携を
自治体学校 経験交流し閉会
社会保障・食と農・民営化など
東京都で開かれていた「第67回自治体学校~ともに学ぶ地方自治が切りひらく平和で豊かな社会」は27日、11分科会・講座と2現地分科会を開催し、閉会しました。分科会では社会保障の切り捨てとのたたかいや、くらしを守る運動、環境や食を守る取り組みなど、全国の経験や課題などを交流しました。
社会保障の充実を議論する分科会では、佛教大学の長友薫輝准教授が「病床11万床削減」「OTC類似薬の保険外し」などの医療費削減の問題点を指摘。「医療は供給が需要を決定する」という大原則に立ち、住民が医療を利用しやすい地域づくりが必要だと述べました。
持続可能な農と食のあり方を考える分科会では、関耕平島根大学教授が、現在の食料危機の背景に、農山村の疲弊や都市生活の不安定化といった構造的問題があると指摘。地域の有機農家から農産物を優先的に公共調達し、学校給食や自治体の配食サービスに活用することで、地域経済を支える仕組みが不可欠だと訴えました。
自治体民営化に関する分科会では、尾林芳匡弁護士が、民営化で行政が多くの非正規雇用者を生み、消費購買力や公共財など地域活力を奪い、「利益は東京や国外の大企業に流れる点に経済的本質がある」と指摘。世界で進む鉄道や電力などの再公営化の事例を紹介し、反対運動では公園・水道・学校・図書館・保育など横の連携をつくっていくことが重要だと指摘しました。
脱炭素や再エネ、環境保全の取り組みを交流する分科会では、NPO地域づくり工房の傘木宏夫氏が、東京都昭島市の物流・データセンター計画で住民が独自に環境アセスメント(評価)を行う活動や、太陽光発電など危険地域での再エネ乱開発により災害が発生している事例などを紹介。再エネ開発の3原則として(1)持続可能性アセスメント(2)地域内再投資力(3)国際連帯―をあげました。
次回の自治体学校は2026年7月11、12両日、大阪府で開催予定です。