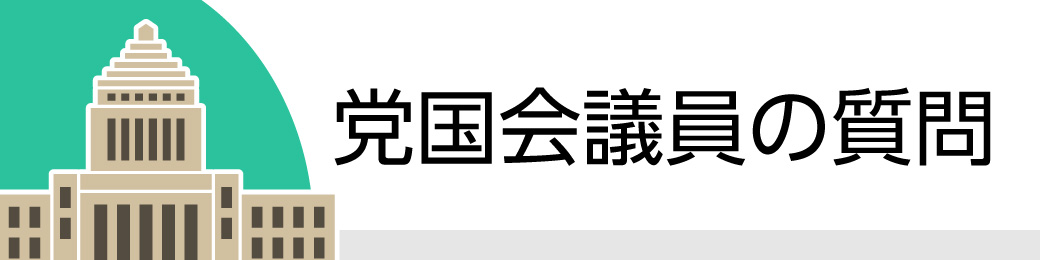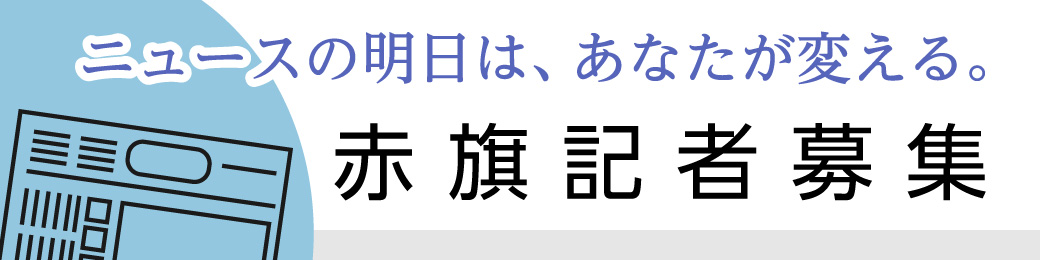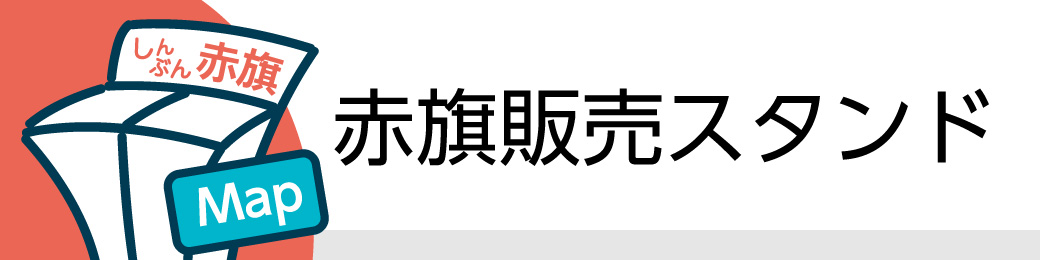2025年7月28日(月)
主張
異常気象と温暖化
科学の蓄積を未来に生かそう
6月の国内の平均気温は、平年を2・34度も上回り、1898年の統計開始以来、最高を更新しました。全国153の気象台などの122地点で過去最高を記録。全国的な異常高温が続いています。
気象学者らでつくる「極端気象アトリビューションセンター」は、同月中旬の記録的高温について「人為起源の地球温暖化がなければ起こりえなかった」と分析しました。
気象庁と文部科学省がまとめた『日本の気候変動2025』は、温室効果ガス排出削減などの対策が不十分だと、産業革命前には「100年に1回」しか起こらなかった高温現象が、今世紀末には100年に99回、つまりほぼ毎年発生すると推定。最新の科学的知見は、手をこまねいていれば、温暖化が進んで“異常気象”が日常の出来事になってしまうと警告しています。
■2世紀かけた知見
約200年前、フランスの数学者フーリエは、大気の存在が惑星の表面温度を上昇させる温室効果の概念を提唱しました。1896年には、スウェーデンの化学者アレニウスが大気中の二酸化炭素濃度の増加と地球の気温上昇の関係を定量的に示しました。
米国の科学者キーリングがハワイで二酸化炭素の継続観測を開始したのは1958年のことです。そのころからコンピューターで再現した仮想地球で気候変動を調べる研究が加速。真鍋淑郎(しゅくろう)博士(2021年ノーベル物理学賞受賞)らが気候シミュレーションの基礎を築きました。
人間活動による気候変動への懸念が高まるなか、1979年に世界気候会議が開かれました。88年には気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が設立されました。
IPCC評価報告書が改定されるたび、人間活動の影響についての表現が変化してきました。90年に公表された第1次報告書は「気温上昇を生じさせるだろう」という表現でしたが、95年の第2次報告書は「影響が全地球の気候に表れている」に。温暖化の主要な原因が人間活動である可能性について、2001年の第3次報告書は「可能性が高い」でしたが、その後「非常に高い」「極めて高い」と確度が増し、21年公表の最新の第6次報告書では「疑う余地がない」と踏み込みました。
■死者数3倍の報告
近年、コンピューターの高性能化とプログラムの改良により、人間活動の影響を量的に評価できるようになりました。今年6~7月に欧州で発生した熱波では、温暖化によって死者数が3倍に増加したという報告もあります。
国際司法裁判所は23日、気候変動は「緊急かつ存亡にかかわる脅威」であり、各国が対策を取る法的義務を負っているとする勧告的意見を出しました。一方、米トランプ政権が地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」離脱を宣言し気候研究や観測の予算を削減したり、日本でも参政党がパリ協定離脱を主張したりするなど逆流もあります。
異常気象が日常化しつつあるいま、人類が、積み重ねてきた科学の成果を、地球の未来に生きる次世代のために、社会システムの変革につなげられるかが問われています。